アーロン氏と親交40年米記者が特別寄稿 差別に負けぬ静かな闘士 愛された品格と豪打
ハンク・アーロン氏死去

Photo By AP
【トム・ホードリコート記者 追悼特別寄稿】ハンク・アーロン氏は大リーグの歴史に残る強打者だが、一人の人間としてはもっと偉大だと、多くの米国民が口をそろえる。40年近い親交があったミルウォーキー・ジャーナル・センチネル紙のトム・ホードリコート記者(66)がアーロン氏を追悼し、スポニチ本紙に特別寄稿した。
22日午前、アーロンの訃報が入ると、私は真っ先にバド・セリグ(前MLBコミッショナー)に電話した。2人は同じ1934年生まれで、親しい間柄だった。セリグは「私は彼こそが、私の年代で最高の野球選手だったと主張しているが、一人の人間としてはもっと素晴らしかった」と言った。アメリカは偉大な人物を失った。とても悲しい日だ。
アーロンとの出会いは82年。私がブレーブス傘下の3Aリッチモンドで野球記者としてのキャリアをスタートさせた時、彼はブ軍のマイナーの育成部長だった。頻繁に3Aの球場に来たが、スーパースターなので観客席に座るわけにはいかず、たまたま記者席で私の隣に座ったのが始まり。後に私の妻になるトリッシュは、3AのアシスタントGMで、アーロンの仕事を手伝っていた。彼が私たちの仲を取り持ってくれたと言ってもいい。
アーロンはベーブ・ルースの通算本塁打記録を抜くなど、当時、パワーヒッターの記録をことごとく塗り替えた。だがルースほど目立った存在にならなかった。それはミルウォーキーやアトランタのような地方都市でプレーしたからだろう。彼がプレーした60~70年代は「ゴールデンエージ(黄金期)」と呼ばれ、野球の社会的注目度が高かったが、脚光を浴びたのはニューヨークのスター、ウィリー・メイズやミッキー・マントルらだった。
性格的にも、アーロンは慎み深く、物議を醸すような発言はしない。プレースタイルも派手ではなく、1メートル83、81キロと体も大きくなかった。ただ手首が強かった。バットスピードが並外れていたから本塁打を量産できた。
そんな彼が全米の注目を集めたのは、74年にルースの本塁打記録に挑戦したとき。人種差別主義者から嫌がらせの手紙が届き、脅迫も相次いだ。でも、彼はそのことに憤慨したりすることはなく、黙々とプレーを続けた。彼はアメリカ社会における自分の役割をよく理解していた。公民権運動の中で、マーティン・ルーサー・キングやジャッキー・ロビンソンは声を上げ、社会を変えていったが、彼は静かに戦い続け、アフリカ系米国人の子供たちのお手本になった。
アーロンは今年1月5日、多くの黒人がためらっているという新型コロナウイルスのワクチン接種をテレビカメラの前で受けた。「私が接種すれば、アフリカンアメリカンが心配することもなくなるだろう」と話した。本当に優しく、品格があり、人々のお手本だった。それがハンク・アーロンという男だ。 (ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル紙記者)
◆トム・ホードリコート 1954年生まれ、バージニア州リッチモンド出身の66歳。バージニア大卒。リッチモンドの地方紙で野球記者となり、85年からミルウォーキー・ジャーナル・センチネル紙でブルワーズ担当。02年から2年間、ニューヨークでヤンキースを担当したが、再びミルウォーキーに戻り現在に至る。日本選手では野茂英雄、松井秀喜、青木宣親らを取材。
2021年1月24日のニュース
-

ダルビッシュ 「サイ・ヤング賞」を諦めた瞬間を告白「これでなくなったって思いました」
[ 2021年1月25日 00:27 ] 野球
-

ダルビッシュにとって変化球とは「家族以外のもので唯一執着するもの」
[ 2021年1月24日 23:20 ] 野球
-

桑田真澄氏 上原浩治氏相手に熱く指導論語る「傾斜を制すれば勝てる投手になれる」
[ 2021年1月24日 23:14 ] 野球
-

ダルビッシュ 野球人口の減少に持論 「誰がこの時代に坊主にしたいねんっていう話」
[ 2021年1月24日 22:55 ] 野球
-

清原和博氏 野球界の後輩と再会したことを報告「嬉しかった!!だから今日はパワー全開」ファンも喜ぶ
[ 2021年1月24日 21:28 ] 野球
-

阪神・スアレスが入国「リーグ優勝、日本一を成し遂げることができるように」 今後は14日間自宅待機
[ 2021年1月24日 20:50 ] 野球
-
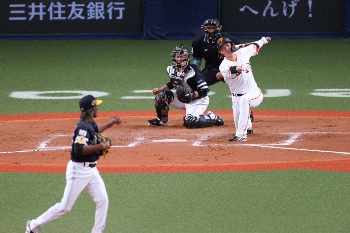
巨人・坂本「モイネロは1年に1、2回の対戦では打てない」と脱帽 日本シリーズは「思い返したくはない」
[ 2021年1月24日 20:36 ] 野球
-

さすが坂本!3000安打達成へ避けて通れないコンバートも「まだ大丈夫です」とキッパリ
[ 2021年1月24日 20:00 ] 野球
-

ソフトバンクの王貞治会長が新人選手を視察 ドラ1井上に「シャープで鋭い。チームリーダーを目指して」
[ 2021年1月24日 19:40 ] 野球
-

巨人・坂本 転機になった9年前の合同自主トレ 原監督に「行きたいならオレが言ってやる」と背中押され…
[ 2021年1月24日 19:30 ] 野球
-

中日ドラ1、高橋宏斗が休憩時間返上でブルペン見学 柳の投球に「全てが想像を上回る投球」
[ 2021年1月24日 16:27 ] 野球
-

巨人の直江がブルペン投球 昨年10月の椎間板ヘルニア手術からの復活へ「徐々に力を入れていく」
[ 2021年1月24日 15:39 ] 野球
-

昨年、白血病公表した北別府さん「直近で今の医療を経験した私からの助言です」と摂津さんにエール
[ 2021年1月24日 14:44 ] 野球
-

巨人 平内&伊藤 1軍キャンプへ「精度を上げていきたい」
[ 2021年1月24日 14:43 ] 野球
-

BC埼玉 元楽天・佐藤由規の入団を発表
[ 2021年1月24日 14:41 ] 野球
-

中日・橋本侑樹投手 一般女性と結婚 中学3年から交際8年「妻のためにも一軍で活躍できるように」
[ 2021年1月24日 13:47 ] 野球
-

DeNA牧「1日1日を大切に」 池谷「がむしゃらに」 1軍キャンプへ意気込み
[ 2021年1月24日 12:13 ] 野球
-

DeNAドラ1入江「爪あとを残したい」 キャンプ1軍スタートへ意気込み
[ 2021年1月24日 11:51 ] 野球
-

【21年版・球界“新”士録9】広島ドラ5・行木 ケガと“無給生活”乗り越えた150キロ元独立リーガー
[ 2021年1月24日 08:30 ] 野球
-

心境変化で茶髪に!?日本ハム・玉井と1年ぶり再会 今季目標は「50試合登板」と「結婚」
[ 2021年1月24日 08:30 ] 野球
-

池田V戦士・江上光治氏 八尾ベースボールクラブのコーチに就任 全日本クラブ選手権初出場目指す
[ 2021年1月24日 08:00 ] 野球
-

【内田雅也の追球】「伸びる選手」の着目点 ハンク・アーロン氏が問いかけた「学ぶ気があるのかどうか」
[ 2021年1月24日 08:00 ] 野球
-

ソフトB・西田広報 現役引退後に転身 明るい人柄評価され29歳で抜てき
[ 2021年1月24日 07:02 ] 野球
-

西武・服部広報 アナウンサーから転身 聞き取りやすい声と正確な言葉遣いの持ち主
[ 2021年1月24日 07:01 ] 野球
-

ロッテ・和中広報 ダウンタウン浜ちゃんの耳打ちに驚き…吉本興業マネジャーから異色の転身
[ 2021年1月24日 07:00 ] 野球
-

東海大農学部 原巨人にリモート差し入れ キャンプ無観客も母校変わらぬ支援
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

巨人ドラ1・平内が決意「初日からアピール」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

5年連続日本一へ“KKコンビ始動”!ソフトバンク・工藤監督 小久保ヘッドに任せた!
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

元ソフトバンク・摂津正氏、慢性骨髄性白血病「骨髄の提供者が増えることを願って」公表
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

中日・仁村2軍監督 2年目の石川昂にハッパ「巨人・岡本の上を行かないと」 キャンプ“地獄”練習予告
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

中日・福田 復帰の福留から「勉強したい」 キャンプはともに2軍スタート
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

楽天ドラ4・内間、宝刀「亜大ボール」で左打者斬る!ブルペン捕手も絶賛「凄いよ」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

DeNA・三浦監督 春季キャンプ“激”競争ヨロシク!1、2軍入れ替え激化期待
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

ロッテ・二木 自身初の10勝へ直球勝負「空振りやファウルを取れれば」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

日本ハム・野村 3年目で初の1軍キャンプ レギュラー定着へ「本当に大事な年」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

ヤクルト・長谷川 自主トレともにしたお股ニキ氏から新球フォークのススメ
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

西武ドラ6・ブランドン、憧れダル目指す!キャンプ1軍スタートには「驚いた」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

西武・与座「サブマリン会」で「発見」 牧田&高橋礼から握り伝授
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

オリックス・佐野 イチ流打撃で「1番・中堅」狙う 「良い方にハマり出しています」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

オリックス ドラ4中川颯 “サブマリン会”への入会熱望 「僕にないものもある。共有してみたい」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

プロ2年未勝利の日本ハム・柿木 1勝の同期・輝星にライバル心「今年はやるしかない」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

広島ドラ1栗林 初ブルペンで“リミッター解除” 「キャンプに入ったらマイペースとはいかない」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

広島・奨成 巨人・小林の「金言」で開眼の予感 「新たな発見。全部うまくいきそうなイメージ」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

阪神ドラ4栄枝 キャンプはステイブルペン!投手と“密”な関係築くぞ 会食なくても心配なし!
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

阪神ドラ2伊藤将 開幕1軍へターゲットは同級生の浅間&渡辺 「対戦できたら勝てるように」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

阪神・高橋 “能見流”で直球磨く 「キャンプでもそこを大前提に」 被打率アップで改良決意
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

阪神・馬場の大化け予告 藤川球児氏「何かが変わった瞬間、何投げても打たれない」 藤浪も高く評価
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

ロッテ・吉井投手コーチ「好奇心がある選手が伸びていく」 指導者講習会でパネリスト
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

王貞治氏 アーロン氏悼む「選手のかがみ 全て凄かった」 同じ時代に生まれた2人の“キング”
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

張本勲氏 アーロン氏追悼「素晴らしい右打者で打ち方が大好きだった」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

ボンズ氏 アーロン氏追悼「彼は象徴であり、伝説であり、真のヒーローだった」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

アーロン氏と親交40年米記者が特別寄稿 差別に負けぬ静かな闘士 愛された品格と豪打
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

アーロン氏 黒人リーグ経てデビュー 中傷の手紙捨てず反骨心に変えた
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

バイデン大統領 偉大なレジェンドアーロン氏へ敬意「白人至上主義の悪意の力をせき止めた」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

作家・佐山和夫さん 過去にアーロン氏の自伝翻訳「ジャッキー・ロビンソンの後を引き継ぎ…立派な人生」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

ヤンキースからFAのマー君 去就なお決まらず 移籍先候補が次々先発補強
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

エンゼルスGM 大谷二刀流復活に期待「ブレークする年になるだろう」
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

元メッツ監督のジョンソン氏 コロナ感染 現在は退院し静養中
[ 2021年1月24日 05:30 ] 野球
-

10年ぶりVへ所信表明 中日・柳「2桁勝利」 梅津「怪我しない」 大投手との合同トレで手応え
[ 2021年1月24日 05:00 ] 野球


























