福島敦彦氏 4強は全て近畿勢、打倒・大阪桐蔭を目標に全体がレベルアップした証拠

Photo By スポニチ
【総評】第103回全国高校野球大会で、「迫球甲子園」で連日、試合を評論した福島敦彦氏が大会を総評した。
2年ぶりの開催となった大会は雨による7度の順延、コロナ禍で2校が大会中に出場辞退するなど想定外のことが起こった。選手のコンディション調整も難しかったことは容易に想像できる。
そんな中、優勝した智弁和歌山は開幕から2週間後に初めて初戦を戦い、6日間で4試合。看板の強打は試合ごとに実戦勘を取り戻して上昇曲線を描き全試合で2桁安打を放った。先制し一度もリードを許すことなく頂点に立ったのは、堅い守りがあったからで2試合に先発し決勝でもピンチの場面で救援したエース中西君は優勝の立役者といっていい。内野手も4試合で失策1。攻守に隙がなかった。就任3年目で選手時代に続く全国制覇となった中谷監督も感無量だと思う。
初めて決勝に進んだ智弁学園は小坂監督が主将だった95年の4強を超えての準優勝。西村、小畠の両投手に前川君、山下君ら1年時から主力を張った選手が確実に成長した好チームだった。
今大会は初めて近畿勢が4強を独占。雨の影響で他のチームが練習会場の確保に困る一方で、自校で練習できる有利さは確かにあったが、全国屈指の強豪校である大阪桐蔭打倒を目標としてきたことが、近畿全体のレベルアップにつながった。
大会を通じては、終盤にもつれる展開が多く、準々決勝3試合を含めサヨナラが8試合、1点差も13試合など僅差のゲームが目立ち球趣を高めた。零封試合が10試合で2桁得点は3試合のみ。地方大会を経験したとはいえ、打者の実戦不足は否定できず「投高打低」の傾向となった。
気になったのはバントのミス。第1ストライクから決められず攻撃の流れをつかめないケースが多々、見られた。地味な作戦だが改めて重要性を感じた。
大会運営が難しい中で、球児から元気をもらった大会だった。(報徳学園、慶大、中山製鋼元監督)
2021年8月31日のニュース
-
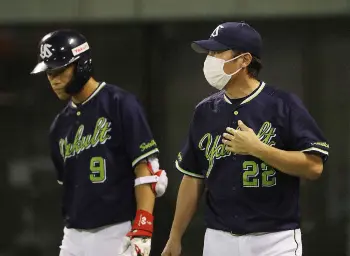
ヤクルト16安打猛攻も及ばず 高津監督「相手にとっても嫌でしょうし、この勢いをつなげたい」
[ 2021年8月31日 22:29 ] 野球
-

昇格即結果の阪神・マルテ 甲子園での試合に喜び「100%のプレーを見せることをみんなと約束」
[ 2021年8月31日 22:22 ] 野球
-

巨人 ヤクルト下し首位キープ 原監督は中川の好リリーフ絶賛「あの場面で0点とはお見事」
[ 2021年8月31日 22:20 ] 野球
-

再び露呈した虎の泣き所 及川が7回に3失点でジ・エンド 矢野監督「7回をどう乗り切るか考えてるけど」
[ 2021年8月31日 22:12 ] 野球
-

巨人・吉川「汗だくわっしょいです」 地元での活躍に喜び「やっとプロに入って“恩返し”出来た」
[ 2021年8月31日 22:07 ] 野球
-

楽天 頼れる島内が決勝の16号3ラン リーグトップの75打点 「死ぬ気で戦っていく」
[ 2021年8月31日 21:51 ] 野球
-

求む、救世主 阪神・矢野監督が2軍戦で好投した高橋の近日中の1軍復帰を明言「準備が整った」
[ 2021年8月31日 21:49 ] 野球
-

上原浩治氏 ロッテの本拠地1000勝を祝福 首位と1・5差に「パ・リーグでいま一番勢いがあるチーム」
[ 2021年8月31日 21:41 ] 野球
-

巨人 ヤクルトとの“壮絶”首位攻防第1R制す!地元凱旋・吉川が3安打4打点と大暴れ
[ 2021年8月31日 21:38 ] 野球
-

ビエイラ NPB外国人投手最多記録並んだ!31試合連続無失点達成 球団記録も更新
[ 2021年8月31日 21:30 ] 野球
-

阪神 甲子園に戻っても断ち切れない「流れ」 一時5点差追いつくも今季ワースト4連敗
[ 2021年8月31日 21:23 ] 野球
-

ロッテ・井口監督「1000勝という時に監督として携われて非常に良かった」
[ 2021年8月31日 21:07 ] 野球
-

甲子園を沸かせた中日・福留の「恩返し」 44歳のベテランが古巣阪神から今季初打点となる決勝適時打
[ 2021年8月31日 21:04 ] 野球
-

ロッテ・美馬 今季5勝目が本拠地1000勝のメモリアル「記念すべき1000勝の時に勝てたのは嬉しい」
[ 2021年8月31日 20:57 ] 野球
-

阪神 7回の好機で登場した代打・佐藤輝が空振り三振 連続打席無安打は「26」に
[ 2021年8月31日 20:52 ] 野球
-

ソフトB東浜自己ワースト3被弾で5回途中KO 「絶対にしてはいけないことをしてしまった」
[ 2021年8月31日 20:50 ] 野球
-

5試合ぶりに復帰の西武・森、11試合連続安打も チームは1分け挟んで3連敗
[ 2021年8月31日 20:40 ] 野球
-

巨人・吉川 地元“初凱旋”で3安打4打点の大活躍!サイクル安打達成にも大手
[ 2021年8月31日 20:36 ] 野球
-

阪神 埋まらない「7回の男」 3番手・及川が福留に痛打浴びるなど3失点 登板3試合連続失点
[ 2021年8月31日 20:36 ] 野球
-

ロッテ 5連勝でZOZOマリン通算1000勝!美馬、メモリアル勝利に花を添える7回1失点で今季5勝目
[ 2021年8月31日 20:21 ] 野球
-

これぞ助っ人の働き 1軍復帰したばかりのマルテが走者一掃の同点適時打 阪神5点差追いつく
[ 2021年8月31日 20:02 ] 野球
-

阪神・青柳、まさか…防御率1位右腕が今季ワーストタイの5失点で5回降板
[ 2021年8月31日 19:53 ] 野球
-

ロッテ・美馬 7回1失点で今季5勝目の権利を持って降板 チームは勝てばZOZOマリン通算1000勝
[ 2021年8月31日 19:50 ] 野球
-

ヤクルト・小川 2カ月ぶり1軍復帰初戦 巨人との首位攻防戦先発も4回途中4失点で降板
[ 2021年8月31日 19:38 ] 野球
-

巨人・中田 激走&炎のヘッドスライディング 17打席ぶり安打から同点の生還
[ 2021年8月31日 19:28 ] 野球
-

巨人・吉川 地元“凱旋弾”に喜び「応援がすごかった」 長良川球場プロ初出場第1打席が本塁打
[ 2021年8月31日 18:32 ] 野球
-

ヤクルト青木 巨人との首位攻防で先制ソロ
[ 2021年8月31日 18:18 ] 野球
-

横浜スタジアムで五輪金の野球、ソフトボールの選手に花束贈呈 ソフト・清原はセレミニアルピッチ
[ 2021年8月31日 18:02 ] 野球
-

中田問題で日本ハム・川村球団社長兼オーナー代行が公式サイトに謝罪文掲載 「皆様を失望させてしまった」
[ 2021年8月31日 17:59 ] 野球
-

【ファーム情報】阪神がウエスタン新の14連勝 オリックスはドラ2・元がサヨナラ打
[ 2021年8月31日 17:56 ] 野球
-

阿佐ヶ谷姉妹がダブル始球式 ロッテ―西武戦で
[ 2021年8月31日 17:53 ] 野球
-

阪神・佐藤輝 今季初の2戦連続スタメン落ち 「助っ人トリオ」の中軸で連敗脱出や 中日戦スタメン
[ 2021年8月31日 17:24 ] 野球
-

アマ野球界を救え!「侍ジャパン」チャリティーオークション開催へ 収益金は各連盟に寄付
[ 2021年8月31日 17:15 ] 野球
-

【31日プロ野球見どころ】セ3強の首位争いは? 西武・栗山は2000安打へあと4本
[ 2021年8月31日 17:00 ] 野球
-

ロッテ小窪獲得 新天地で入団会見 V争い中のチームで「新井さんや黒田さんのような存在に」
[ 2021年8月31日 16:14 ] 野球
-

阪神2軍 リーグ新記録の14連勝 広島に13安打12得点で大勝
[ 2021年8月31日 16:00 ] 野球
-

NPB木内審判員が新型コロナ陽性 27~29日の中日―巨人戦出場、同試合の審判は全員隔離待機
[ 2021年8月31日 15:47 ] 野球
-

阪神・高橋遥人 2軍戦で5回1/3を無失点の好投 6戦で計17回1/3を1失点
[ 2021年8月31日 14:55 ] 野球
-

ヤクルト 新助っ人ケリン・ホセ投手を獲得「日本でプレーする事を夢見て頑張ってきました」
[ 2021年8月31日 14:52 ] 野球
-

ドジャースのウリアスがハーラー単独トップの15勝目 首位ジャイアンツとは1・5差
[ 2021年8月31日 14:42 ] 野球
-

東京五輪金の侍ジャパン オークションに直筆サイン入りユニ出品 収益金でアマチュア野球支援
[ 2021年8月31日 14:35 ] 野球
-

ブルージェイズのゲレロJRが2発 エンゼルスの大谷とは4本差
[ 2021年8月31日 14:23 ] 野球
-

阪神・藤浪が合流 2日の中日戦で先発へ…2軍戦では12Kの圧倒的パフォーマンス
[ 2021年8月31日 14:01 ] 野球
-

阪神・大山、佐藤輝らが早出特打 不振脱出へ振り込み
[ 2021年8月31日 13:49 ] 野球
-

大谷 3試合ぶり42号ソロで4の1 ゲレロらに4差 チームは連勝 前戦右手首投球直撃で9・1登板回避
[ 2021年8月31日 13:48 ] 野球
-

日本ハム・宮田輝星 2年目での支配下選手契約に笑顔「素直にうれしく思います」
[ 2021年8月31日 13:36 ] 野球
-

ロッテ「ALL for CHIBA」イベント開催 CHIBAユニホームを着用
[ 2021年8月31日 13:14 ] 野球
-

【31日の公示】ロッテは小窪、日本ハムは宮田、ヤクルトはケリンを支配下選手登録
[ 2021年8月31日 12:58 ] 野球
-

ア・リーグ東地区首位のレイズが8連勝 新人フランコは30試合連続出塁
[ 2021年8月31日 12:58 ] 野球
-

阪神 勝てばウエスタン新記録の14連勝 高橋遥人が先発
[ 2021年8月31日 12:34 ] 野球
-

大谷翔平 3試合ぶり特大42号ソロで勝ち越し! 前戦右手首投球直撃で9・1登板回避も打撃には問題なし
[ 2021年8月31日 12:24 ] 野球
-

日本ハム 俊足が武器の宮田と支配下選手契約 背番号69
[ 2021年8月31日 11:27 ] 野球
-

ロッテ、元広島・小窪獲得 「光栄に思います」
[ 2021年8月31日 10:04 ] 野球
-

大谷翔平 9・1の登板回避 29日に右手首に投球直撃 マドン監督「問題はないが痛みが残っている」
[ 2021年8月31日 09:18 ] 野球
-

巨人 貢献度高い高橋&戸郷 切磋琢磨する同期コンビ
[ 2021年8月31日 09:00 ] 野球
-

レンジャーズ有原、米国での長期離脱語る 右肩動脈瘤から9・2復帰戦「万全です」
[ 2021年8月31日 07:39 ] 野球
-

金本知憲氏 不振の阪神・佐藤輝へ提言 俺なら「弱点」の内角高めをあえて狙う
[ 2021年8月31日 07:00 ] 野球
-

阪神・平田2軍監督語録 リーグ新14連勝に「選手たちが集中力をずっと保ってくれた。素晴らしいわな」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

巨人・原“家康”中5日解禁 「いと楽し」ヤクルト、阪神と6連戦「関ケ原」「大坂夏の陣」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

巨人・秋広 母校・二松学舎大付に負けぬ活躍を!
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

ヤクルトのライアンに地の利 0.5差で追う首位・巨人とのカード初戦先発
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

阪神・青柳 9連勝かけ31日先発 虎では18年ぶり快挙へ 対戦防御率0・89でも中日警戒
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

阪神 いくぞG倒&再奪首ローテ! ガンケルを中8日で巨人2戦目に配置 “第6の男”には藤浪を抜てき
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

阪神・マルテ 48日ぶりに1軍昇格 アルカンタラに代え、攻撃力アップで再奪首狙う
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

虎党が選ぶ9月のキーマンは大山 4番復帰&Vロードけん引をみんな期待
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

阪神・中野 ついにヒッティングマーチ完成! 31日中日戦でお披露目 「背中を押してもらえる」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

西武・栗山 通算2000安打達成へ「手応えはあります」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

西武・栗山 9.3誕生日に2000安打達成なら史上初 あと4本
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

ロッテ・美馬 球団マリン1000勝へ気合「マリーンズに来て何もやっていないので」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-
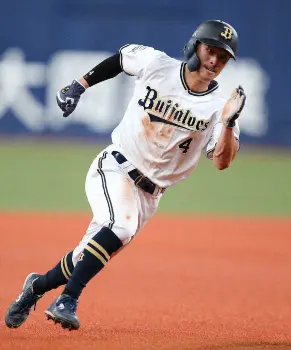
オリックス・福田 2年ぶり規定打席へ「数字はあまり見ないように」 自然体で残り試合もけん引
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

日本ハム 先発ローテ再編!上沢 中8日で首位・オリ戦初戦先発
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

楽天・早川 初宮崎でパ全5球団制覇だ!6.6以来の勝利へ指揮官も期待
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

ソフトバンク・東浜 13年ぶりの宮崎で恩返し快投誓う 「一人一人全力で」 キャンプ地から逆襲だ
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

ソフトバンクの育成・重田がコロナ陽性 球団は3軍全体のPCR検査を実施予定も1、2軍の活動に影響なし
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

ソフトバンク・育成3年目渡辺陸が支配下契約 栗原先輩に続くぞ 「長所の打撃で息の長い選手になりたい」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

広島・森下 五輪金メダルの地・横浜“凱旋”で輝き再び!!DeNA斬ってチームを5連勝に導く
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

広島・大瀬良が右肘手術決断のツインズ・前田を心配「まだまだ元気に投げる姿が見たい」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

広島・玉村 高卒2年目左腕では球団初の先発3勝に挑む 9月1日先発見込み、01年河内の2勝を超える
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

9・2DeNA戦に先発予定の広島・九里 四球減らして自己最多の9勝目を目指す
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

DeNA浜口 久々の本拠・ハマスタに「帰ってこられてうれしい」 広島の左打者警戒
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

5球団6選手が支配下契約 巨人・鍬原「与えられた場所でしっかり投げていければ」 DeNA宮国も
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

智弁和歌山 学校に優勝報告、午後には早くも新チーム始動 新主将は岡西佑弥内野手
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

イチロー氏 甲子園制した智弁和歌山の練習環境を称賛 「絶対に抜けない。意識が違う」
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

福島敦彦氏 4強は全て近畿勢、打倒・大阪桐蔭を目標に全体がレベルアップした証拠
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

全国高校軟式野球 作新学院6年ぶり日本一 エース小林が4安打完封 中京は“4連覇”ならず
[ 2021年8月31日 05:30 ] 野球
-

「ツ、ツ、ツギョー!」 パイレーツ・筒香の逆転サヨナラ場外弾に実況も大興奮 移籍後13戦5発
[ 2021年8月31日 02:30 ] 野球
-

パイレーツ・筒香の打撃に中畑清氏が太鼓判「始動が早くなりグリップとボールの距離がしっかり取れている」
[ 2021年8月31日 02:30 ] 野球
-

エンゼルス・大谷の最終成績は? MLB公式サイトのデータ分析担当記者が緊急予想
[ 2021年8月31日 02:30 ] 野球
-

担当記者が予想 エンゼルス・大谷は波に乗れば55本塁打可能 水原通訳も「もう一度流れがくる」
[ 2021年8月31日 02:30 ] 野球
-

エンゼルス・大谷の“モノマネSHOW”チームメートに大好評
[ 2021年8月31日 02:30 ] 野球
-

ロイヤルズ・ペレス 5試合連発38号でリーグトップのエンゼルス・大谷に3差
[ 2021年8月31日 02:30 ] 野球























