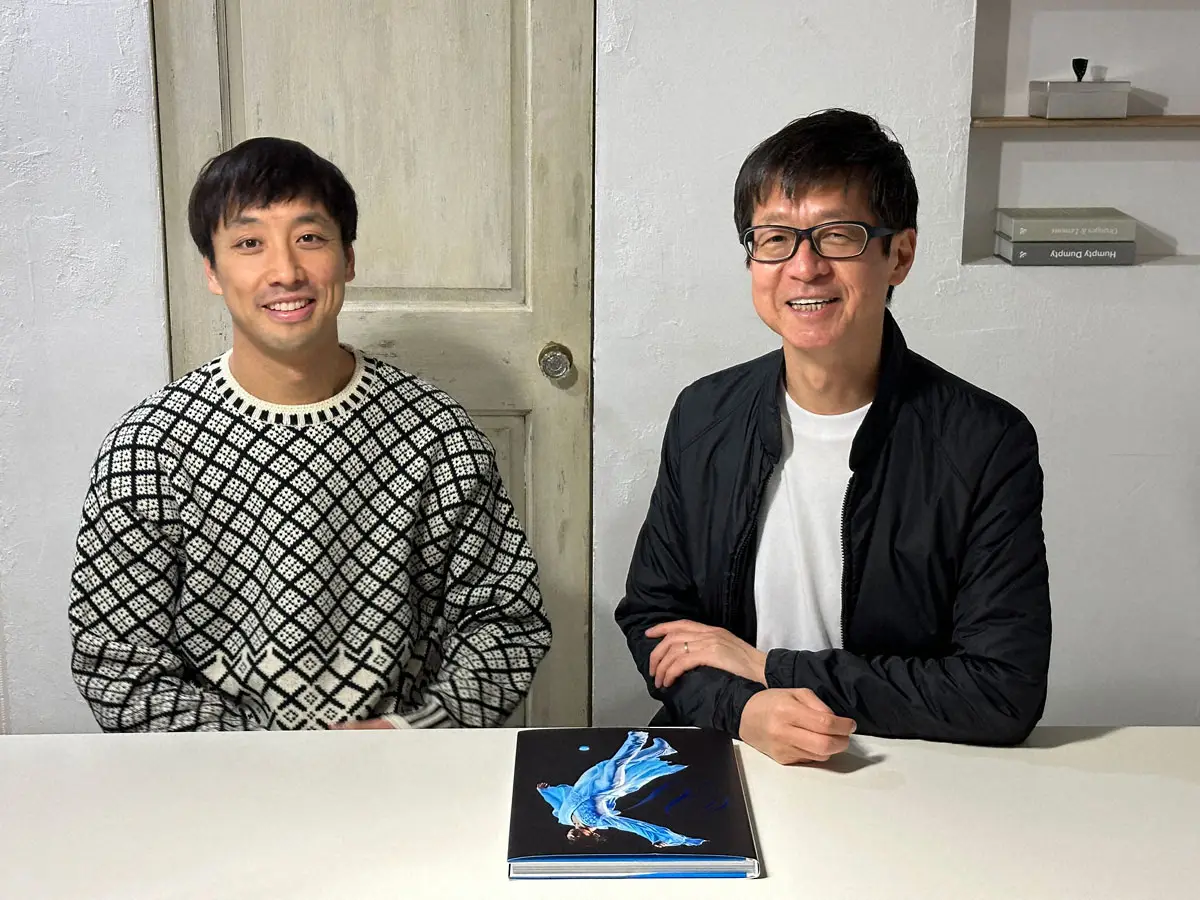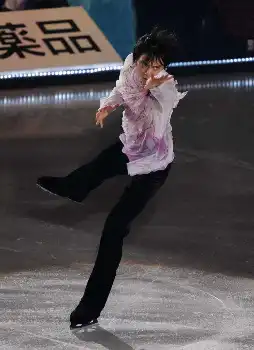米国のスポーツを書くために必要なこと(2)=単位と時間編

Photo By スポニチ
【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】1995年8月7日、スウェーデン・イェーテボリで行われた陸上の世界選手権で、ジョナサン・エドワーズ(英国)が18メートル29の世界記録を樹立。社内のテレビで中継を見ていた私は日本時間の午前零時直前に編集トップの指令ですぐにそれを裏1面に仕上げるべく、突貫工事で原稿を書いた。
ただし後になって知ることになるのだが、米国での反応は日本以上だった。なにしろ18メートル29を“米国式単位”で換算するとちょうど60フィート(実際には18メートル28センチと7・64ミリ)。「初の60フィート到達」というキリのいい数字が米国では関心を集めた。
このように米国で使われている長さ、重さ、速度の単位、さらに温度表示は日本とは異なっている。スポーツの原稿を書いていると、各選手の身長、体重、さらにバスケで言えば3点シュート、野球なら本塁打の距離は計算機のお世話にならないと(珠算上級者は別格?)日本では“商品”にはならない。
長年こんな仕事をしているせいもあって、私は1フィート=0・304794メートル、1インチ=2・5399センチ、1ポンド=0・45359キロ、1ヤード=0・9144メートル、1マイル=1609メートルまでは換算するときの数値として覚えている。大谷選手の本塁打の距離はもちろんすべてフィートで表示されるので、計算機でその数字に0・304794をかけてメートルにしている。
ただし身長は手間がかかる。なぜならフィートとインチの両方で示されるからだ。レイカーズの八村塁選手の身長は6フィート8インチ。だから(6×0・304794)+(8×2・5399)で203センチということになるが、1人ならまだしも、何人も選手の身長を記さなければならないときも多いので、これだけはいちいち計算してはいられない。
というわけで5フィートちょうど(152センチ)からNBAの複数のビッグマンの身長でもある7フィート6インチ(228センチ)までは1インチ刻みですぐにセンチに換えられるようにすべて覚えている。6フィートちょうどが183センチで、7フィートは213センチ。6フィートを基準にすると、上に1インチずつ行くごとに2センチ→3センチ→2センチ→3センチと交互に増え、7フィートでは上に3センチ→2センチとその逆のパターンで増えていくことを頭の中に入れている。
体重は各自まちまちなので覚えきれないが、220ポンドがだいたい100キロであることは認識している。最初にフィートやポンドの換算が業務上必要になってしまった人は、まず自分のサイズを米国式に変えておくとその数字を身近に感じるかもしれない(私は5フィート7インチ+1/4インチで143ポンド)。
気温も日本では摂氏だが米国では華氏。換算式が複雑なので、これはネットの換算サイトにすべてお任せしているが、それでも華氏32度が摂氏0度、華氏86度が摂氏30度であることだけは覚えている。さらにアラスカとハワイ両州を除くと東部、中部、山岳部、西部で時差があってサマータイムも採用しているので、米本土では4×2の8通りの時間と、それに伴う日本との時差が存在するのもお忘れなく。取材対象がどこにいるかによって、試合開始の日本時間は大きく変わってくるし、もし米国内出張時がサマータイムの開始もしくは終了日であれば、その日に時計を1時間進めたり、遅らせたりする作業を怠ると、自分が乗るべき飛行機をぼう然と見送ったり(同業の記者に被害者1人存在)、空港に早々と到着しすぎて時間を持て余したりするので気をつけてほしい。
面積もエーカー、ヘクタールなど日本とは違うが、平方キロ・メートル、あるいは平方メートルに換算したあとに比較対象としてよく用いているのは東京ドームの敷地面積(0・047平方キロ・メートル)と東京23区の面積(619平方キロ・メートル)の2つ。面積は長さほどピンとこないので、換算したあとの日本流?のフォローが必要になってくる。
単位以外で私が最初にNBAの米国でやったときに戸惑ったことがある。
それが試合における時間表示。日本では何かが起きた瞬間は開始からの経過時間を記すことが多いが、米国ではNFLを含めて残り時間で表記するのが主流となっている。これはボクシングでも同じ。画面を見ていると日本の放送では時間が3分ちょうどに向かって進んでいるが、米国などでは0に向かって少なくなっている。
試合の時間経過はネットの中で「Play―by―Play」を見ていればわかるのだがこれもNBAでは1クオーター12分から0に向かって突き進んでいくパターン。90年代中盤、現地でNBAの取材をしていたときには試合後にメディア用のゲーム・スタッツ(個人&チーム成績)と「Play―by―Play」が紙の資料として配布されるのだが、ただでさえ時間を節約しなくてはいけないときにゆっくり見てはいられない。ましてやそこに記されているのはすべて残り時間なので、経過時間を書く当方の原稿用紙(まだそんな時代)には反映されない。なので私は試合を見ているときには必死だった。ノートにはプレーごとの両チームの得点経過を書いているが、そのたびに12分から場内表示の時間を引き算して書く作業を繰り返していた。
アナログの時代はもう終わっているのでそんな面倒くさいことは必要はないのだが、それでも頭の中を“逆算型”にしておくことはある意味、この仕事の基本でもある。
さて単位や時間表記をふまえた上で、もっと大事なことがある。それは英語への理解力。私は学生時代から英語を勉強していたわけではなく、「米国に1人で行け」と会社の指示を受けてから学習(苦闘?)を始めた人間なので、すべてがほぼゼロからのスタートだった。だからある程度、英語に熟達した人に比べると、感じたことや見えた世界が少し違う。その中から、これから第1歩を踏み出す人に私なりに印象的だった“スポーツ英語”を紹介してみたいと思う。(続く)
◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には7年連続で出場。還暦だった2018年の東京マラソンは5時間35分で完走。
2023年8月28日のニュース
-

【バスケW杯】日本は29日に豪州戦 河村「勝てばパリ五輪がほぼ決まる」アジア勢総崩れで追い風
[ 2023年8月28日 22:40 ] バスケット
-

ラグビー日本代表 W杯登録メンバー変更 ヘルと中野が離脱→ファカタヴァと下川を登録
[ 2023年8月28日 20:54 ] ラグビー
-

バスケ男子のホーバス監督を東京五輪銀の“教え子”が賞賛「冷静に考えて、トムさんすごくない?」
[ 2023年8月28日 19:53 ] バスケット
-

新小結・錦木「“遅かったな”より“頑張ったな”」史上3位、所要103場所でのスロー昇進に感慨
[ 2023年8月28日 19:31 ] 相撲
-

日大アメフト部 リーグ戦発表会見には参加せず 関東学生連盟理事長は「今の問題を解決するのが先決」
[ 2023年8月28日 18:19 ] アメフト
-

【バスケW杯】日本協会が空席問題説明 あすオーストラリア戦以降も一般向けにチケット再販へ
[ 2023年8月28日 18:12 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本と「18点差」にまつわる物語… 「記憶にない」屈辱から「経験ない」歓喜に
[ 2023年8月28日 18:00 ] バスケット
-

バレーボール高橋藍がバスケ河村勇輝から「いい刺激をもらえた」アジア選手権から帰国
[ 2023年8月28日 16:56 ] バレーボール
-

佐渡ケ嶽親方、新関脇昇進の琴ノ若へ「私とではなく先代と並んでほしい」将来の琴櫻襲名を期待
[ 2023年8月28日 16:16 ] 相撲
-

【バスケW杯】フィンランド戦でMVP級活躍ホーキンソンの豪州との不思議な縁「すごく楽しみ」
[ 2023年8月28日 15:42 ] バスケット
-

新関脇・琴ノ若「師匠の番付に並んだのはすごく光栄」大関獲り足固めへ「まだまだ上を目指して精進」
[ 2023年8月28日 15:39 ] 相撲
-

アメフト関学大 前人未到の甲子園ボウル6連覇を懸けたシーズンへ 9月1日、リーグ戦が開幕!
[ 2023年8月28日 15:04 ] アメフト
-

アジア制覇のバレー男子日本代表が帰国 石川「特別な雰囲気を味わい、そこで勝てて自信になった」
[ 2023年8月28日 12:33 ] バレーボール
-

【秋場所新番付発表】叔父・朝青龍のアドバイスで白鵬以来の新大関優勝へ 豊昇龍が会見
[ 2023年8月28日 12:29 ] 相撲
-

渡辺雄太“もう休んで”足を心配する声に「検査して、重傷ではないのを確認」「本当にだめなときは出ない」
[ 2023年8月28日 12:14 ] バスケット
-

笹生優花 米CPKC女子OP最終日73と伸ばせず8位もティーショットに手応え「きのうよりは少し安定」
[ 2023年8月28日 11:48 ] ゴルフ
-

渡辺雄太「昨日の雰囲気最高でした」 空席埋めたファンに感謝「急遽チケット買ってきてくださって…」
[ 2023年8月28日 11:37 ] バスケット
-

畑岡奈紗が最終日に猛チャージ!米CPKC女子OP、68で13位「いいスコアにつながり良かった」
[ 2023年8月28日 11:33 ] ゴルフ
-

渋野日向子、米ツアーCPKC女子OPは50位 スコア伸ばせずも「ショットの内容的には良かった」
[ 2023年8月28日 11:25 ] ゴルフ
-

菅沼菜々 お面&綿菓子のお祭りスタイル披露に「可愛い~」「アイドルなーちゃん誕生」
[ 2023年8月28日 10:08 ] ゴルフ
-

セロトニンを増やす飲み物は?コンビニでも買える3つ【コメントつき】
[ 2023年8月28日 09:00 ] MELOS
-

サザエさん症候群の人へ。憂うつな気持ちを紛らわせるかもしれないコラム
[ 2023年8月28日 09:00 ] MELOS
-

セロトニンを増やすにはどんな食べ物がいい?おすすめ一覧
[ 2023年8月28日 09:00 ] MELOS
-

オートミールをご飯代わりにすれば痩せる?管理栄養士の回答
[ 2023年8月28日 09:00 ] MELOS
-

「漸進性(ぜんしんせい)の原則」とは。トレーニング5原則
[ 2023年8月28日 09:00 ] MELOS
-

米国のスポーツを書くために必要なこと(2)=単位と時間編
[ 2023年8月28日 08:50 ] バスケット
-

ブックメーカーのオッズを覆した日本 倒したのは米国が“土台”のフィンランド
[ 2023年8月28日 08:28 ] バスケット
-

【バスケW杯】ホーキンソン ダブルダブルで歴史的1勝の最優秀選手に!「最高に感動した」の声
[ 2023年8月28日 07:00 ] バスケット
-

【バスケW杯】河村&富永 22歳コンビ躍動で歴史的大逆転!2人だけで42点「凄さが知れ渡った」の声
[ 2023年8月28日 06:45 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本・比江島 歴史的1勝に勢いつけた前半FG100%!「前半の活躍が大逆転に…」の声
[ 2023年8月28日 06:30 ] バスケット
-

【バスケW杯】豪州のパティ・ミルズ W杯で16試合連続2桁得点!ドイツ戦でも21得点マーク
[ 2023年8月28日 06:15 ] バスケット
-

大相撲秋場所番付発表 錦木が史上3位のスロー新三役昇進 琴ノ若は新関脇昇進で父に並ぶ
[ 2023年8月28日 06:00 ] 相撲
-

【記者の目】バスケW杯空席問題 必ず空席を作らないという事前の取り決めをするべき
[ 2023年8月28日 04:45 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本 18点差逆転で17年ぶり1勝 11戦全敗の欧州勢から歴史的白星
[ 2023年8月28日 04:45 ] バスケット
-

【バスケW杯】空席目立つから一転 渡辺「トムさんの発言と僕のツイートの効果があったなら良かった」
[ 2023年8月28日 04:44 ] バスケット
-

【バスケW杯】中原雄氏 守備切り裂いた!河村が勝たせたフィランド戦
[ 2023年8月28日 04:43 ] バスケット
-

龍神NIPPON パリへ収穫V 完全アウェーでイランを完全制圧 エース石川MVPでけん引
[ 2023年8月28日 04:42 ] バレーボール
-

道産子・菊地絵理香 地元V 運も味方に「マジで嫌」PO制した
[ 2023年8月28日 04:41 ] ゴルフ
-

日本代表、イタリアに完敗 不安払拭できず…堀川隆延氏 バックスリー連携強化を
[ 2023年8月28日 04:40 ] ラグビー
-

田中希実 5000メートル8位入賞 左足流血も勇気の猛スパート
[ 2023年8月28日 04:39 ] 陸上
-

ロコ・ソラーレ 今季初戦で貫禄V ボディビル挑戦の藤沢「カーリングを思い出すのに苦労したが…」
[ 2023年8月28日 04:38 ] カーリング
-

輝鵬が新十両昇進祝賀会で初まげ披露 壇上で鼻血のハプニングも「やっぱ持ってますね」
[ 2023年8月28日 04:37 ] 相撲
-

高橋健治さんトップ グロス80、ネット71.6
[ 2023年8月28日 04:30 ] ゴルフ