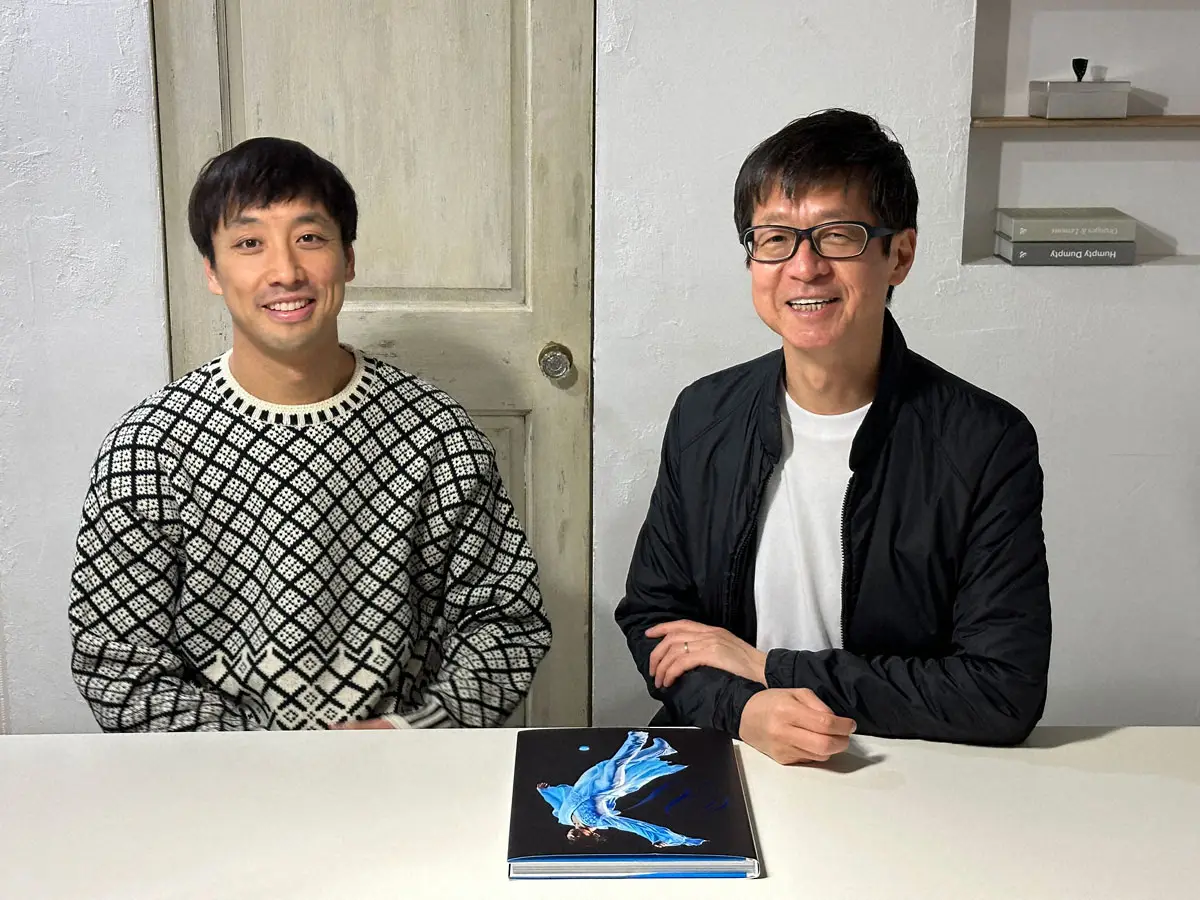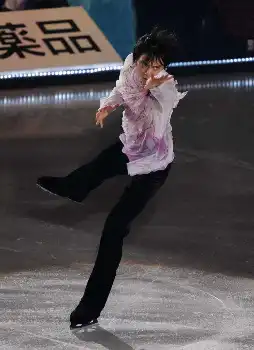終戦記念日によみがえる悲しい過去と不透明な未来 スポーツともリンクする“負の歴史”

Photo By スポニチ
【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】1945年3月22日。太平洋戦争の激戦の地、硫黄島では1932年のロサンゼルス五輪の馬術競技(障害飛越)で金メダルを獲得していた“バロン西”こと西竹一大佐が42歳で戦死。その16日前、米軍では海兵隊に所属していた27歳のハリー・オニール中尉が死亡しているが、彼は1939年、フィラデルフィア・アスレチックスの捕手としてたった1試合だけ出場した“元大リーガー”だった。
守っただけで打席数はなし。オニール中尉は年齢を考えれば、戦争が終われば再びメジャーに復帰しようとしたとしたのではないかと思われるが、彼の“未来図”は西大佐同様、硫黄島にすべてを飲み込まれた。1打席も記録していないメジャー経験者は映画「フィールド・オブ・ドリームス」でもサイドストーリーとして描かれているが、オニール中尉にも「なんとしても打席に立ちたい」という切実な思いがあったのではないだろうか…。
第二次大戦中の米国の人気スポーツはボクシング、競馬、大リーグ、そしてアメフト。その後“火の球投手”として歴史に名を刻むことになる大リーグ・インディアンズ(現ガーディアンズ)のボブ・フェラーは真珠湾攻撃を受けた翌日に海軍に志願して入隊した。戦艦アラバマの対空砲部隊のチーフとして従軍。同じ海の上にはやがて撃沈される輸送船に乗っていた巨人の沢村栄治がいた。
NBAはまだ存在せず、バスケットボールは米国民が注目する人気競技ではなかった。しかし戦争とは他の競技とは別な観点で密接な関係を持ち合わせている。
1937年、中西部一帯で13チームで創設されたバスケのプロ・リーグがNBL。人気競技ではないので運営は難しいはずだったが、このリーグを資金面で支えたのはファイアストンとグッドイヤーのタイヤメーカーと世界的な総合電機メーカーのゼネラル・エレクトリック。この3社は30年代後半から40年代にかけて軍需産業で活況を呈し、それがスポーツへの“投資”に回ることになった。
八村塁(25)が所属しているレイカーズはそのNBLで誕生し、1948年に対抗組織だったBAAに組み込まれた。BAAが49年にNBLを吸収合併してNBAと改称するのだが、もし戦争がなく軍事産業が不用で平和な時代だったならばNBLは有能な選手を集めることができず、やがてNBAの人気チームとなるレイカーズは誕生していなかったかもしれないというもうひとつの歴史がこの“裏側”に潜んでいる。
1980年代後半、米国内を渡り歩いてカレッジ・フットボールを取材していたとき父親をベトナム戦争で亡くしたという2人の選手と出会った。大学は違っているので2人に接点はない。しかし「炎に包まれたヘリコプターで仲間を先に脱出させたときに機体が爆発。それで命を落とした」という“父の最期”は同じだった。
1人目にはさらなる詳細を求めたが、2人目にはそれ以上、質問はしなかった。彼らの目は「父親は仲間の命を救ったヒーローであってほしい。そう信じているからこそ悲しみを乗り越えることができたんだ」と訴えているようだった。真実はわからない。しかしそこに踏み込むのは彼らの“誇り”を踏みにじるものではないかと思い、私にはできなかった。それから20年後、インターネットで検索すると、ベトナム戦争で亡くなった米軍ヘリコプターのパイロットと搭乗員は併せて約5000人。なぜ私が短期間で同じ境遇の選手に立て続けに出会ったのかは、長い年月が経過してようやく理解できた。
ロシアのウクライナへの軍事侵攻はまだ終わりが見えない。NBAではホーネッツのスビアストラフ・ミハイリューク(26)とキングスのアレックス・レン(30)の2選手がウクライナ出身だが、22年2月に侵攻が始まって以来、彼らの不安と心配はウクライナ国民同様に尽きないことだろう。
八村や渡辺両選手の活躍もあってNBAのウエアや帽子といったアイテムを購入された方も多いかもしれない。そのグッズには必ずNBAの公式ロゴが記されているはずだ。ドリブルしている姿がシルエットとなっているが、それはレイカーズの元スーパースター、ジェリー・ウエスト氏(85)がモデルになったもの。しかしその“ヒーロー”は1951年6月、10歳年上の兄デビッドさんを朝鮮戦争で失っている。
著書「WEST BY WEST」には「仲間を戦火の中で助けた」という兄の最期の状況が、ウエスト家に伝えられたと書かれてある。ただし当時13歳だったウエスト少年は家族からその知らせを聞いたのではなく、小さな町の“ご近所さん”から「お兄さんが亡くなったそうで…」と声をかけられたという。それがどれほど心を傷つけたのかは本人だけにしかわからないと思うが、あのシルエットの向こう側には、戦争で心を痛めた少年の姿があることを忘れないでほしい。
宇宙物理学者の故ホーキング博士は著書「ビッグ・クエスチョン―人類の難問に答えよう」の中にこう記している。
「次の千年間のどこかの時点で核戦争または環境の大変動により地球が(人の)住めない場所になるのはほぼ避けられないと見ている。地球を離れようとすれば、地球規模で力を合わせなければならない」
どうやれば新天地を見つけられるかを考えているであろう?未来の人にとって、宇宙からは見えない国境という人間が引いた勝手な線ををめぐって武器を使って争う姿はとうてい理解できないかもしれない。
きょうは終戦記念日。本当はもっと早く迎えるべき日だったはずで、そうであれば多くの命が救われていたことだろう。散っていった人たちの無念さを無駄にしてはいけない。私にはスポーツのいうアングルでしか切り取ることしかできないが、その小さな世界にも悲しみと怒りが渦巻いている。“終戦”という言葉が持つ意味。きょうはどんな形であれ、それを自分に問うべき大事な1日だと思う。
◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、佐賀県藤津郡嬉野町(現・嬉野市)で生まれ、北九州市小倉区(現・小倉北区)で育つ。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。
2023年8月15日のニュース
-

渡辺雄太が負傷退場…W杯ぶっつけも ホーバス監督「フランス戦は出さない。スロベニア戦も分からない」
[ 2023年8月15日 22:50 ] バスケット
-

バスケ日本代表 渡辺雄の負傷交代も…富永が6本の3Pシュート含む20得点の大活躍!アンゴラに逆転勝利
[ 2023年8月15日 21:05 ] バスケット
-

三菱地所、ラグビー日本代表の必勝祈願祭を開催 姫野主将と「ONE TEAM」の大切さ強調
[ 2023年8月15日 20:46 ] ラグビー
-

渡辺雄太 第3クオーター終了間際でベンチに戻る ファン「本戦に影響ないといいな」と心配の声続々
[ 2023年8月15日 20:41 ] バスケット
-

【世界陸上】泉谷駿介「決勝は安全圏」圧倒的自信でブダペスト出発 鵜沢飛羽、田中佑美は初舞台
[ 2023年8月15日 20:31 ] 陸上
-

バスケ日本代表・富永 アンゴラ戦で前半から11得点!“和製カリー”にファン大興奮「やっぱえぐい」
[ 2023年8月15日 20:14 ] バスケット
-

バスケ日本代表に暗雲…渡辺雄太、強化試合で右足首負傷か 苦悶の表情浮かべ右足を引きずり控室へ
[ 2023年8月15日 19:56 ] バスケット
-

ラグビー日本代表落選の山中亮平 代表引退せず「2027年W杯目指します」「諦めるのは性に合わない」
[ 2023年8月15日 18:31 ] ラグビー
-

競泳日本代表らが異例の不満解消ミーティング 梅原競泳委員長「コミュニケーション不足だった…反省」
[ 2023年8月15日 16:42 ] 水泳
-

ラグビーW杯日本代表 3人欠員が最大のサプライズ 追加選出どうなる?
[ 2023年8月15日 15:20 ] ラグビー
-

ラグビー日本代表・李承信、初のW杯メンバー入り「山中さんとナキ。2人の分まで」
[ 2023年8月15日 13:04 ] ラグビー
-

ラグビー日本代表W杯メンバー 平均年齢は28・8歳 15、19年大会から横ばい
[ 2023年8月15日 11:47 ] ラグビー
-

姫野主将「歴代最高の主将に」先輩・流からは「頼りないので僕がサポートする」ラグビーW杯日本代表発表
[ 2023年8月15日 11:22 ] ラグビー
-

V・ウィリアムズが1回戦を突破 世界ランク20位以内の選手に勝ったのは4年ぶり
[ 2023年8月15日 11:12 ] テニス
-

ラグビーW杯日本代表 姫野主将「日本代表をさらなる高みへ」選手コメント一覧
[ 2023年8月15日 10:48 ] ラグビー
-

ラグビー日本代表 No・8姫野和樹がW杯で初の主将
[ 2023年8月15日 10:30 ] ラグビー
-

ラグビー日本代表 FB山中亮平が落選へ 9月開幕W杯フランス大会最終登録メンバー発表
[ 2023年8月15日 10:26 ] ラグビー
-

ラグビー日本代表 9月開幕W杯メンバーに姫野、リーチら30人選出 ケガで残り3人は未定
[ 2023年8月15日 10:20 ] ラグビー
-

【全日本大学選抜相撲十和田大会】団体戦は東洋大が6年ぶりV 個人戦は日大・花岡真生が今季2冠目
[ 2023年8月15日 10:12 ] 相撲
-

お盆休み明け憂鬱な人は、“ストレッチ”でだるさを解消!【動画解説】
[ 2023年8月15日 09:00 ] MELOS
-

学校や会社に行きたくなくなったらどうしたらいい?心理カウンセラー回答
[ 2023年8月15日 09:00 ] MELOS
-

【体験談】退職祝いでもらって嬉しいものランキング!迷ったらコレをあげれば間違いない
[ 2023年8月15日 09:00 ] MELOS
-

「仕事やめたい」は甘えなの?“職場の人間関係”が退職理由の場合
[ 2023年8月15日 09:00 ] MELOS
-

終戦記念日によみがえる悲しい過去と不透明な未来 スポーツともリンクする“負の歴史”
[ 2023年8月15日 07:45 ] スポーツ社会
-

重量挙げ 三宅宏実さんが結婚 法大後輩のリオ代表・中山陽介さんと
[ 2023年8月15日 04:45 ] 重量挙げ
-

バスケ男子W杯メンバー決定 ホーバス監督「サバイバルを終えてベストメンバーを選べた」
[ 2023年8月15日 04:44 ] バスケット
-

松山英樹 PO第2戦滑り込み 猛チャージ1イーグル4バーディー65で16位
[ 2023年8月15日 04:43 ] ゴルフ
-

畑岡奈紗 風に散った11位 序盤から崩れた2ダブルボギー
[ 2023年8月15日 04:42 ] ゴルフ
-

ウクライナ 24年パリ五輪に参加方針 事実上立場を転換
[ 2023年8月15日 04:41 ] 五輪