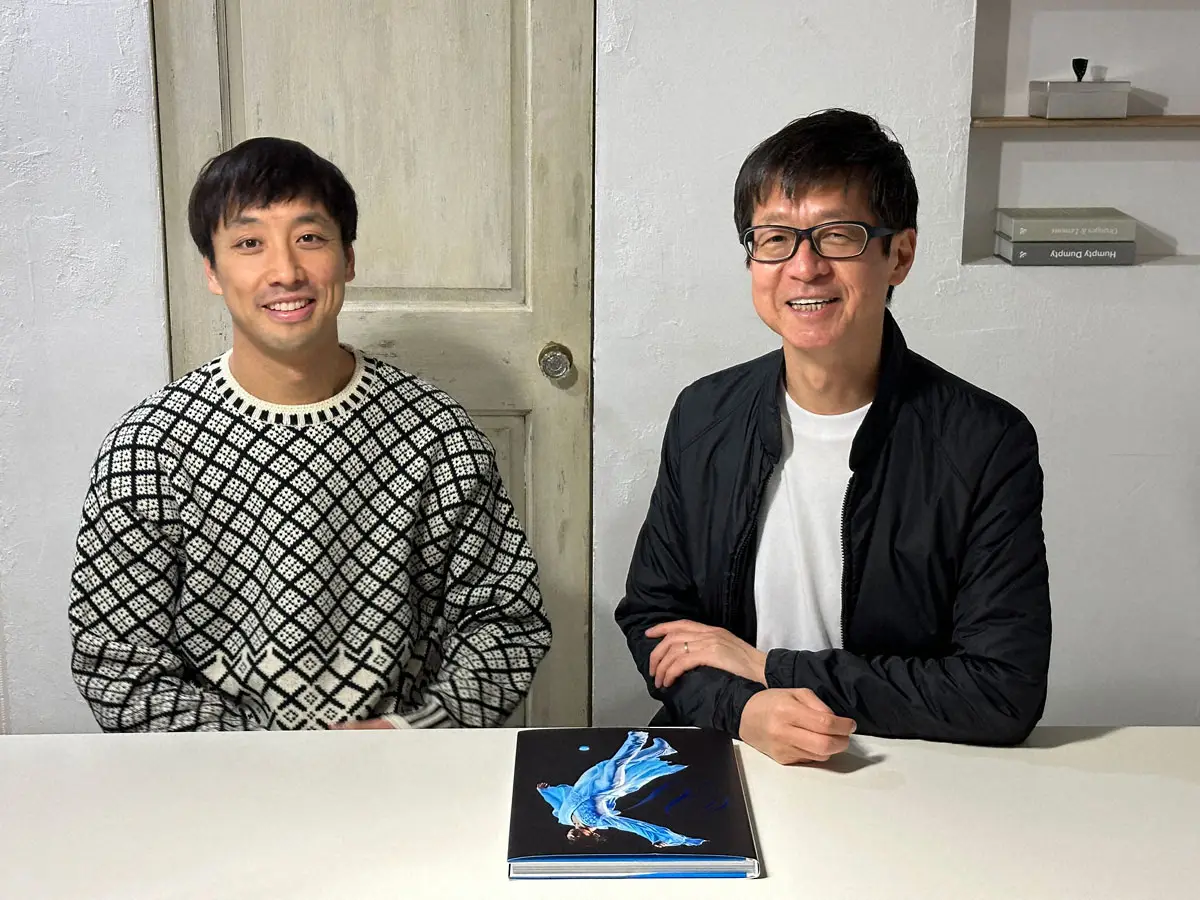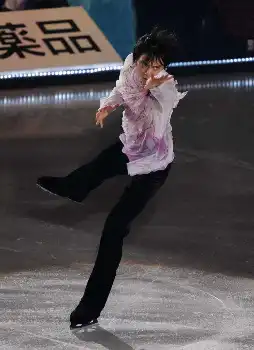米国のスポーツを書くために必要なこと(終)=コラムと未来編

Photo By スポニチ
【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】スポーツだけでなくどんなジャンルの電子版“商業コラム”にはある程度の鉄則がある。しかも起承転結を整えようとする一般的な作文や小論文とは少し違う。思ったことをそのまま書き連ねるわけにもいかない。自分の意見を一人称のまま全部ぶちまけようとすると反発を買ってしまうこともある。
まず冒頭部分はある意味“命”かもしれない。広げた新聞紙ではなく小さなスマホで読む人がほとんどなので、出だしでつまらないと思われると画面をスクロールしてくれないので、最初はどうしてもキャッチーな言葉が必要になる。
起承転結は構成的に否定はしないが、冒頭にまずオチに等しい「結」をもってきて“先制攻撃”をかましておかないと、そこから先は読んでもらえないと覚悟したほうがいい。なので最後には「第2の結」が必要。これは本題の噺(はなし)に入る前の「まくら」で笑わせておいて、最後に「サゲ」がある落語にも似ている。
しかし全部読んでもらうには最初と最後だけでなく、各文節に間断なくアクセント的な要素を随所に散りばめていくスタイルが理想型で、漫才コンビ「笑い飯」のダブル・ボケ(ダブル・ツッコミ?)のようなアップテンポな展開が長年にわたってコラムを書くときの私の理想だった。(一度も成功したことはなかったが…)。「ちょっとご相談がありまして」と悠長に切り出していると、すぐに「ちょっと何言っているか分からない」と読み手に見放される世界である。
何を言いたいのかはコラムの見出しになる部分。だからといって、どんなに知識と経験と論理展開に自信があっても、一人で「自分の考えはこうだ」と突っ走るのはやめよう。同じ意見を持つ著名人の談話や意見、関連する数値が明確なデータ、同じ場面を物語る身近な情景にできるだけ力を借りよう。そもそも読み手との接点がない(に等しい)のだから、まずその距離を埋めていくことがコラムを書く上での努力目標でもある。
俳句はとても参考になると思っている。たった17文字で情景、時間経過、色彩、匂い、心情などを伝えられる“技術”を持っているからだ。直接的な物言いはせず、違う事象や事物にそれを託して、読み手に言わんとしていることを想像してもらう。この日本独自の文芸の手法に従っていれば、たとえ長い文章であっても言外に良質の“文字なき主張”が生まれるし、そこがコラムニストが密かに狙っている部分。だからプレバトに出演されている夏井いつき先生や特別永世名人の梅沢富美男さんは、たぶんスポーツ・コラムニストになっていても、いい文章を書いていたのではないかと思う。
「漫画のマにイロハのイ。稽古のケにルビーのル。中黒(・)を入れまして新聞のシに濁点、小さな羊羹のヨ。音引き(―)を入れまして太鼓のタに濁点と終わりのン」
私が入社した80年代前半にはファクスさえない取材現場があった。社内には速記部門があって、原稿は電話で送稿。そのとき外国の人物などを表記するカタカナには“字解き”という作業があって、たとえばマイケル・ジョーダンを原稿化したいときには、公衆電話の周囲にいる人が怪訝な表情を見せる中で受話器に向かってこんな風につぶやいていた。
しかしアナログは去り、デジタルが時代を席巻している。さらに人工知能(AI)が人間社会を包み込むようになり、いくつかの職業はやがてAIに取って代わられると言われている。
記者業もそのひとつ。取材対象が会見などで口にしたことや、試合展開と個人成績だけの単純な原稿であれば人間より早く出稿が可能なのだろう。これも時の流れだ。だからこそこれからスポーツ・ジャーナリズムに身を投じる人は、これまで以上にその人にしかできない“こだわり”が必要だ。でないと次々にAIがそつのない原稿を短時間で書いてしまう時代がきっと来る。
テレワークの私はひたすら選手や試合そのものに隠れている(と感じた)データを探した。昨季のNBAのプレーオフでは八村選手が所属するレイカーズがファイナルの一歩手前の西地区決勝まで進出したが、第7シードからそこまで勝ち上がったのは1987年のスーパーソニックス(現サンダー)以来、36年ぶり2チーム目だった。個人得点などの通算記録は今のAIでもわかる(たぶん)。しかし第7シードのチームがプレーオフでどんな成績を収めたのかは、過去の年度別プレーオフ成績をひとつずつすべてチェックしないとわからない。
つまり人間の手が加わって初めて生まれるデータのひとつ。もちろん近未来にはそれさえも迅速に処理してしまう超万能型のAI記者が登場するのだろうが、見えないライバルに抵抗しようと思えば、自分で抽出する手作りのデータがきっとものを言う。
調べたのはプレーオフが12チームから16チーム制になった1984年以降の年度別全成績。ノートに1年ごとに書き込んで87年のスーパーソニックスの存在を発見したときには正直うれしかった。もしレイカーズがファイナルまで勝ち進んでいれば第7シードとしては初の快挙だったが、それでも自分で見つけた手書きのデータはレイカーズの原稿の肉となり骨となった。
これが41年間に及んだ私の記者生活最後のコラムになる。悔いはない。広告会社に内定が出ていながら「好きなことをやらせてほしい」と母親を説き伏せて入り込んだ世界。やるだけのことはやった。あとは誰かにバトンを渡したいと思う。
心残りと言えば、このコラムの「第2の結」を探せなかったこと。笑いを取れないのはひとえに私の筆力が未熟だったからだが、やはり最後ぐらいはAIに相談するべきだったか…。
ではどこにいるのかわからないけど、次の走者にバトンを放り投げます。誰なのかはわかりませんが、どこかで受け取ってください。ここまで読んでいただいた方に心から感謝申し上げます。(終)
◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には7年連続で出場。還暦だった2018年の東京マラソンは5時間35分で完走。今後の目標はマスターズ陸上の100メートルで13秒台前半で走ること(無理かな~)。
2023年8月30日のニュース
-

【バスケW杯】日本 最速で31日にパリ五輪切符獲得へ!その条件とは…?
[ 2023年8月31日 01:00 ] バスケット
-

【バスケW杯】アジア勢が3大会連続1次リーグ“全滅” 日本のパリ五輪切符の行方は順位決定戦へ
[ 2023年8月31日 00:12 ] バスケット
-

【バスケW杯】順位決定戦組み分け決定!日本2連勝ならパリ五輪切符獲得 他のアジア勢全敗が“追い風”
[ 2023年8月31日 00:10 ] バスケット
-

【バスケW杯】アジア勢のパリ五輪出場権は順位決定戦へ 中国が敗れて日本の五輪出場の可能性残る
[ 2023年8月30日 23:09 ] バスケット
-

【バスケW杯】スロベニア3連勝!ドンチッチ 第1QまさかのFG0%も…19得点9アシストの活躍
[ 2023年8月30日 22:30 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本 順位決定戦の相手確定!31日ベネズエラ、2日カーボベルデ 2連勝でパリ五輪出場へ
[ 2023年8月30日 22:26 ] バスケット
-

【バスケW杯】ホーキンソン 31日ベネズエラ戦へ「先手取る」疲労で日本語対応はなし
[ 2023年8月30日 22:24 ] バスケット
-

【バスケW杯】スロベニア・ドンチッチ 1QはFG0%…前半まさかのFG成功1本も10得点6A5R
[ 2023年8月30日 21:21 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本次戦の相手ベネズエラ 世界ランク17位の実力国も今大会は故障者続出で苦戦
[ 2023年8月30日 20:24 ] バスケット
-

サニブラウンが競技転向!?サッカーJ1・C大阪の練習着身にまとい「入団希望のFWです」
[ 2023年8月30日 19:38 ] 陸上
-

【バスケW杯】ヨルダンにNBAレジェンド蘇る!?“左利きのコービー”が米国に奮闘「似すぎて鳥肌」の声
[ 2023年8月30日 19:30 ] バスケット
-

【バスケW杯】米国 前回大会の雪辱へ3連勝で1次L首位通過!エドワーズが22得点などヨルダンに完勝
[ 2023年8月30日 19:29 ] バスケット
-

【バスケW杯】えっ!ジョージア―ベネズエラ戦で珍シーン…ダンクミス応酬
[ 2023年8月30日 19:15 ] バスケット
-

【バスケW杯】中国 セルビア3連勝で逆転突破に望み!1次L最終戦結果次第で日本の今大会五輪切符消滅へ
[ 2023年8月30日 18:54 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本と31日対戦のベネズエラ 平均年齢32・25歳のベテラン軍団
[ 2023年8月30日 18:40 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本、31日の相手はベネズエラに決定 56年ぶり2勝目へ日程も後押し
[ 2023年8月30日 18:37 ] バスケット
-

前年覇者の大西魁斗は怒とうの16連戦目で迎える今季国内初戦へ「体が痛くてもゴルフはしたいと思う」
[ 2023年8月30日 15:56 ] ゴルフ
-

若隆景が実戦稽古再開「恐怖心よりも相撲を取れる喜びがある」右膝前十字靱帯断裂から回復順調
[ 2023年8月30日 15:43 ] 相撲
-

DAZN 「ラグビーW杯」日本代表が世界に衝撃を与えた過去の名勝負を配信!
[ 2023年8月30日 14:00 ] ラグビー
-

若元春が霧島と充実の連続18番「体しんどい…」秋場所へ「最低限のハードル」2桁勝利目指す
[ 2023年8月30日 13:40 ] 相撲
-

池江璃花子 ミズノ新水着に好感触「改良された」
[ 2023年8月30日 13:35 ] 競泳
-

霧島が若元春に13勝5敗「2人でもり上がった」途中から「待ったなし」無尽蔵のスタミナ発揮
[ 2023年8月30日 12:24 ] 相撲
-

コートにマリフアナの匂い 全米オープンでハプニング
[ 2023年8月30日 10:20 ] テニス
-

驚きと発見!ソイプロテインにまつわる【興味深い】調査
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

ガリガリが筋トレしても「意味ない、まず太るべき」?体を大きくするメニュー[スポーツナース監修]
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

バーベルスクワットの正しいフォーム、効果的なやり方、重量と回数
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

【腹圧】高める“メリット”や“かけ方”とは。トレーニング方法も解説!
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

筋トレと有酸素運動の「順番」や「時間配分」は?どっちを先にやれば効果的なのか
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

痩せ始めサインは「顔」に出るってホント?痩せていく順番も解説[医師監修]
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

【痩せ始めサイン6つ】ダイエット中に“下痢やおなら”が出る理由は?痩せていく順番も解説[医師監修]
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

港区のおすすめパーソナルジム11選。特徴と料金まとめ
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

ランニングはどれくらいのダイエット効果があるの?
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

運動嫌いでも大丈夫!座ってできるダイエット筋トレ6選
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

【ラグビーW杯】日本代表SO・李承信の父がエール 亡き母の思い背負い…自分と仲間を「信」じて
[ 2023年8月30日 09:00 ] ラグビー
-

「ねじり腹筋」で脇腹ギュッ!ツイスト腹筋トレーニング3種
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

お腹瘦せ&脂肪燃焼のダブル効果!「腹筋ねじりジャンプ」
[ 2023年8月30日 09:00 ] MELOS
-

ビキニフィットネス・ダンシーあずさ Miyakoと“美筋肉”2ショット披露に「ブロック素敵」「凄い」
[ 2023年8月30日 08:13 ] スポーツ
-

米国のスポーツを書くために必要なこと(終)=コラムと未来編
[ 2023年8月30日 07:41 ] スポーツ一般
-

【バスケW杯】日本 世界3位に大健闘 豪に敗戦も明日から順位決定L 渡辺「ここからが本当に勝負」
[ 2023年8月30日 05:30 ] バスケット
-

【バスケW杯】大会初得点の富樫が躍動 14点7アシスト 豪州に敗戦も「自信につなげていい」
[ 2023年8月30日 05:28 ] バスケット
-

【バスケW杯】豪州リーグでもプレーの馬場 守備に追われ5得点のみ 世界3位の強豪に「さすがだな」
[ 2023年8月30日 05:26 ] バスケット
-

【バスケW杯】河村 7アシストも3得点 フィンランド戦の勢いなく「やっぱり悔しい」
[ 2023年8月30日 05:24 ] バスケット
-

【バスケW杯】第3Qで取った35点 五輪切符争いで重要に 富永も打ち続けたことを評価
[ 2023年8月30日 05:22 ] バスケット
-

【バスケW杯】優勝候補ドイツがフィンランドを圧倒 隙なし3連勝
[ 2023年8月30日 05:20 ] バスケット
-

サニブラウン帰国 「9秒8台は全然出る」 やり投げ・北口榛花から刺激も
[ 2023年8月30日 04:40 ] 陸上
-

田中希実が帰国 逆境乗り越え「今後変わるためのよりどころになるのでは」
[ 2023年8月30日 04:38 ] 陸上
-

照ノ富士 来月10日初日の秋場所へ稽古開始 腰は「治ったわけではない」
[ 2023年8月30日 04:20 ] 相撲
-

大の里 初めて白の稽古まわし 「ようやくだなという実感が湧いた」
[ 2023年8月30日 04:18 ] 相撲
-

伯桜鵬は回復途上で休場示唆 無理はせず「夢をかなえるため最善の選択を」
[ 2023年8月30日 04:16 ] 相撲
-

炎鵬 秋場所全休の意向 3場所連続休場も「どこまで落ちても土俵に必ず戻りたい」
[ 2023年8月30日 04:14 ] 相撲
-

【レスリング】藤波朱理が世界選手権へ闘志「まずは世界一。一番の目標はパリ五輪V」
[ 2023年8月30日 04:10 ] レスリング
-

パリ・パラ開幕まで1年 エスタンゲ会長「障がい者に対する社会の見方を変えたい」
[ 2023年8月30日 04:08 ] 五輪
-

【体操】世界選手権女子代表が練習公開 宮田笙子「メダルを狙っていきたい」
[ 2023年8月30日 04:06 ] 体操
-

森木章年が3度目V プレーオフで制し「自分のやりたいゴルフができた」
[ 2023年8月30日 04:00 ] ゴルフ
-

松尾慎祐さんが首位 女性は鶴谷悦子さんが堅首 108ホールチャレンジゴルフ
[ 2023年8月30日 03:58 ] ゴルフ
-

【全米オープンテニス】綿貫陽介1回戦敗退「チャンスはあったが…」
[ 2023年8月30日 02:30 ] テニス
-

【全米オープンテニス】島袋将 シングルス1回戦敗退「気持ちが力みに」
[ 2023年8月30日 02:28 ] テニス
-

【全米オープンテニス】宮崎百合子 4大大会初勝利 日本生まれ、所属は英国
[ 2023年8月30日 02:26 ] テニス