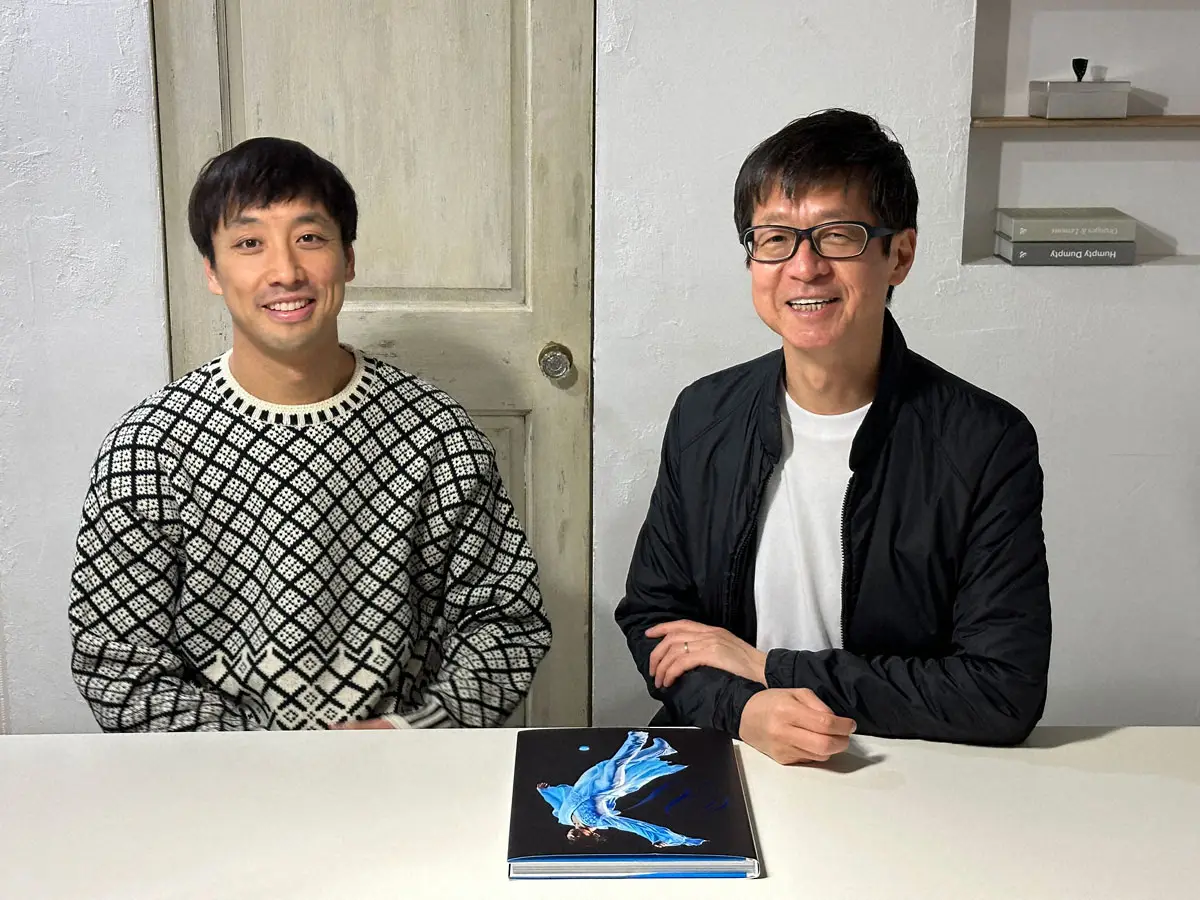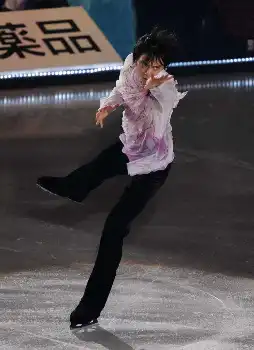米国のスポーツを書くために必要なこと(3)=翻訳&発音編

Photo By スポニチ
【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】米国に足を踏み入れてスポーツの取材を始めた当時、日本の学校で習わなかった英語ばかりで、私にとっては毎日が“未知との遭遇”だった。
ブルズのマイケル・ジョーダンがよく口にしていたのは「DOWN THE STRETCH」で、本来、最後の直線に入った競馬におけるレース終盤の用語。スポーツでは「優勝がかかったシーズン終盤の数週間」を意味していると今ではネットで検索可能となっている。シーズンではなく試合単位でも使われているようで「土壇場で得点を決めるのが自分の仕事」とジョーダンが強調するときの“土壇場”が、「ストレッチの下って何だよ?」と最初に私を当惑させた辞書にはない言葉だった。
「なぜフットボールを始めたの?」。記者になれば質問しないと仕事にならない。でもそれをWHYで始めると「好きだったから」といった味気のない単純な答えしか得られないケースが多かった。
ある時、隣にいた米国の記者がその質問を「WHAT INSPIRED YOU TO START~」で始めた。するとその選手はフットボールを始めた理由を「ベトナム戦争で亡くなった叔父が最初に教えてくれたから」というエピソードを語り始めた。日本の某大手電機メーカーがCMで使っているINSPIREという動詞が「鼓舞する」「感化させる」といった意味であることは知っていたが、記者として一番大事な質問をするときの使い方は教科書には出ていなかった。
NFLやNBAなどでは試合前日までに故障者の情報が掲示される。故障個所とともに記されるのが試合当日に出場する可能性で、現在では(1)QUESTIONABLE(出場か欠場かは半々)(2)DOUBTFUL(75%欠場)(3)OUT(欠場)と表記。しかし私の時代には(4)PROBABLE(5)POSSIBLE(6)QUESTIONABLEが使われていて、私はてっきり(5)が可能性として一番出場しそうな選手だと思っていた。ところが可能性の大きい順に並べると(4)>(6)>(5)。「たぶん」「ありそう」「疑わしい」と覚えていた言葉の故障者におけるニュアンス?がわからず、“可能性の序列”を理解するのには時間がかかった。
言外の意味を読み取らないと選手の本音がわからないときもある。記者会見で「LIKE I SAID…(以前にも言ったように)」と選手や監督が話したときには表情が微妙に違うからだ。1996年のNBAファイナルでジョーダンのいたブルズへの対策を何度も聴かれたジャズのカール・マローンはこの言葉にあとに自身の回答を付け加えたが、その表情たるやまさに鬼。会見出席義務があるがゆえに彼らは壇上に姿を見せるが、時として「前にも言ったように)」には「しつこいぜ。もうしゃべらせるなよ」という本音が見え隠れしていた。逆に言えば「意識はしているさ。でも本当のことは言わないぞ」という意思表示でもあるように見えた。
発音も時としてやっかいな“敵”になる。アルファベットで書けばいい記者はどんな複雑な発音であってもそのまま記せばいいのだが、カタカナに置き換えなくてはいけない日本語を母国語とする記者には知識とスキルを要求される作業になる。
この件についてはかつてのコラムで書いたのだが、RとL、SとCやTHなどを識別できる文字を持たない以上、アルファベットをカタカナにした時点で、そのほとんどが“真実”ではなくなるのだが、長年この作業をしながら、私は可能な限り“近似値”を探し続けた。カタカナであってもその通りに発音すると現地の人、さらに選手本人にもしかしたら通じる状態にしておきたかった。
まず米国ではアクセントのない最後の母音は無音に近い状態になることを理解してもらいたい。なのでMURRAYはUにアクセントがあるのでYの前のAはほぼ聞こえない。カタカナにするとマレーではなくマーリーが正しい…というか「リ」をRの発音にする限りは現地の発音に近い。だからBARKLEYはバークレーではなく「リ」をLの発音にした上でバークリー。最後のEはないと思った方がいい。最後の文字がY関連の名前で言えばRAMSAYはラムジー、LINDSAYはリンジーだ。またYが最後ではない位置にある名前ではそのYが前後の文字に干渉する。だからNBAヒートのBAM・ADEBAYOのラストネームはアデバヨではなくアデバイヨ。かつてグリズリーズに在籍したO・J・MAYO(現在サウジアラビアでプレー)はマヨではなくメイヨー。ローマ字は日本の文字表記に大きく貢献したのは事実だが、こと発音に関してはアルファベットの発音を妨げている側面もある。
MICHAELはマイクル(マイコー?)、JOHNSONはジョンスン、JACKSONはジャクスンと聞こえるはずだが、これもアクセントのない最後の母音は無音に近いから。ただし日本でもかなり昔からマイケル、ジョンソン、ジャクソンとして定着している表記であり、それは「イギリス」「オランダ」といった現実とは違った発音でありながらそのまま認めている我が国の慣習?に従っている。
6月のNBAドラフトで全体トップ指名を受けたのはフランス出身のVICOR・WEMBANYAMA。彼のラストネームをローマ字的な読みでウェンバンヤマと表記しているメディアをよく見かけるが、2番目の「ン」は除外した方が良いと思う。アルファベット系の多くの名前は“奇数”で分解されるからだ(すべてではないけれど)。私はその昔、米国内でホテルの予約を取る際に自分の名前(高柳)のスペルを担当者に説明するときには「TAK」「AYA」「NAG」&「I」と説明していた。母音のAが5つも並ぶという欧米的にはありえないスペルなのでそれをきちんと伝えるにはローマ字感覚を捨てて、彼らに合った奇数単位のリズムが必要だった。
なのでWEMBANYAMAを分解するとWEMBAN+YAMAの偶数単位ではなくWEMBA+NYAMA。するとどうなるかと言えば、ウェンバンヤマではなくフランスのメディアであればNがYAにかかってウェンバニャマ(この場合ファーストネームはビクトル)、米国ではNが無音になってウェンバヤマ(ファーストネームはビクター)と発音しているアナウンサーやリポーターが多い。
WEMBA+NYAMAをカタカナにしたとき「ェ」と「ヤ」のダブルアクセントであるにもかかわらず、フラットなイントネーションを誘発させる2番目の「ン」はどこにも存在せず、本人が「ウェンバニャマ」と自分の名前を発音している動画も存在している。つまりどこにも2つ目の「ン」は見当たらない。
Nがあるのに「ン」を発音しないケースもあれば、その一方でNがないにもかかわらず発音するケースもある。
NFLドルフィンズのエースQBはTUA・TAGOVAILOA。ラストネームについては特集を組んだ米国のメディアもあるくらいなのでよほど珍しかったのだろう。米国式発音ではTUNG―o―vai―LOH―uh。スペル通りに読もうとするとタゴバイローアだが、最初の4文字(TAGO)を「タンゴ」と読むためにタンゴバイローアというカタカナにしないと“近似値”にはならない。
インターネットのない時代だと絶対にわからなかった表記だが、現在では名前に「PRONUNCIATION(発音)」のキーワードを加えただけで発音はわかるし、中にはウェンバニャマのように選手本人が説明している動画なども存在。この手順を踏まないと、カタカナを用いた記事は選手の名前をミスリードしてしまうので、老婆心ながら、米国のスポーツを書く人たちは自分たちに科せられている責任と使命をどこかで感じていてほしいと思う。
通信社の表記に「右にならえ」で合わせていれば業務的には楽かもしれないが、今やどんな人でも少しの手間をかけるだけで、実際の発音をチェックできる時代。些細なこだわりかもしれないが、米国のスポーツを書くという仕事の第1歩はここにあると思っている。
さて最後にコラムそのもの書き方について述べてみる。長年にわたってこんな原稿を書いてきたが、とくに私が“唯一の答え”を持っているわけではないのであくまで参考まで。これからこの道に入る人は、ある意味とてもきつい環境に置かれると思うので“応援歌”のつもりで記しておきたい。(続く)
◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には7年連続で出場。還暦だった2018年の東京マラソンは5時間35分で完走。
2023年8月29日のニュース
-

馬瓜エブリン「追い上げは凄まじかった!」と男子日本代表称える パリ五輪出場権へ「みんなでつかもう!」
[ 2023年8月30日 06:30 ] バスケット
-

【バスケW杯】馬場雄大 延泊して応援の妻・森カンナに「一緒に戦ってくれて感謝してます」
[ 2023年8月30日 00:28 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本のパリ五輪出場権獲得の条件は?アジア勢勝利はまだ日本のみ 暫定2位フィリピン要注意
[ 2023年8月29日 23:05 ] バスケット
-

【バスケW杯】豪州戦“敗因”はスムージー?渡辺雄太 元同僚との抱擁が話題「頭ポンポン最高」「泣けた」
[ 2023年8月29日 22:43 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本・ホーバス監督「フィジカルに負けた」 順位決定戦からパリ五輪へ「絶対勝つ」
[ 2023年8月29日 22:33 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本・ホーキンソン ファンの期待に応えた33得点「アジア1位は絶対できると思う」
[ 2023年8月29日 22:30 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本・富樫 「厳しい戦いだった」豪州に敗戦…パリ五輪出場権へ「切り替えて頑張る」
[ 2023年8月29日 22:16 ] バスケット
-

【バスケW杯】渡辺雄太24得点も実らず…パリ五輪へ順位決定戦「1点1点がパリへの道」「本当の勝負」
[ 2023年8月29日 22:01 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本 ホーキンソン&渡辺雄が奮起も…豪州に完敗で1次L敗退、パリ五輪へ順位決定戦に
[ 2023年8月29日 21:45 ] バスケット
-

【バスケW杯】まるでティモンディ高岸!?日本と対戦、豪州の“そっくりさん”が話題「兄弟みたい」
[ 2023年8月29日 20:55 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本・ホーバス監督 2Q途中に「簡単にやられないで!」と喝!「時には必要」の声
[ 2023年8月29日 20:54 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本 35―57と22点ビハインドで前半終了…2Q途中にはホーバス監督が喝入れる場面も
[ 2023年8月29日 20:48 ] バスケット
-

【バスケW杯】日本 河村、比江島、渡辺雄ら豪州戦のスタメン発表!ドイツ、フィンランド戦から変更
[ 2023年8月29日 20:05 ] バスケット
-

十両・輝鵬が新しい締め込みを初披露 休場明けで左足に不安も“超人的”回復力に期待
[ 2023年8月29日 20:04 ] 相撲
-

122連勝中のレスリング藤波朱理「絶対世界一」9月の世界選手権へ地元で練習公開
[ 2023年8月29日 19:55 ] レスリング
-

向中野改め天照鵬が念願の白まわしで新十両昇進を実感「うれしかった」北青鵬らと申し合い14番
[ 2023年8月29日 19:31 ] 相撲
-

【バスケW杯】ドイツ大勝で「日本強いかも」の声 ノビツキー氏来場でネット騒然「夢のよう」
[ 2023年8月29日 19:27 ] バスケット
-

炎鵬が黒まわしで再始動「まだ体が動くのは神様が与えてくれたチャンス」首の大ケガから復帰へ決意
[ 2023年8月29日 18:40 ] 相撲
-

【バスケW杯】元NBAトップ選手が河村の活躍を大絶賛!ネット「日本の誇り」「TOPに認められた」の声
[ 2023年8月29日 18:38 ] バスケット
-

【バスケW杯】ドイツ 3連勝で1次L突破!シュルーダー15得点、残り1枠を懸けて日本と豪州が今夜激突
[ 2023年8月29日 18:21 ] バスケット
-

谷川美帆が念願の初優勝 九州女子シニアゴルフ速報
[ 2023年8月29日 18:06 ] ゴルフ
-

【バスケW杯】日本が対戦する豪州 中心選手は人気俳優に似てる!?控えにはあの芸人に似てる選手も
[ 2023年8月29日 18:03 ] バスケット
-

スピード昇進の新十両・大の里が初めて白まわし姿に 「やっと関取になれたんだ」と実感
[ 2023年8月29日 15:52 ] 相撲
-

伯桜鵬「あまり状態は良くない」左肩のケガで秋場所へ不安残す 夏巡業の休場は「申し訳ない」
[ 2023年8月29日 15:25 ] 相撲
-

【バスケW杯】日本 豪州戦で先発2人入れ替えへ ホーバス監督「SHOCK THE WORLD!」
[ 2023年8月29日 13:30 ] バスケット
-

サニブラウン「ステップアップできた」世界陸上から帰国 パリ五輪は200メートル出場の可能性も示唆
[ 2023年8月29日 10:28 ] 陸上
-

痩せたいなら「レモン水」!材料2つの簡単すぎる作り方[内科医監修]
[ 2023年8月29日 09:00 ] MELOS
-

こっそりダイエット。周りにバレない“立ちながら筋トレ”3種目
[ 2023年8月29日 09:00 ] MELOS
-

賞味期限切れの納豆、どうする? “食べたら危ない基準”とは
[ 2023年8月29日 09:00 ] MELOS
-

初心者あるある!バーベルスクワットのNGフォームとやり方
[ 2023年8月29日 09:00 ] MELOS
-

米国のスポーツを書くために必要なこと(3)=翻訳&発音編
[ 2023年8月29日 08:40 ] スポーツ一般
-

ドローンの飛行は不可 NY市警がテニスの全米オープンで警告 飛来すれば迎撃システムを行使
[ 2023年8月29日 07:04 ] テニス
-

【バスケW杯】河村 パリ五輪切符獲得へ格上撃破誓う NBA入りアピールも
[ 2023年8月29日 04:45 ] バスケット
-

【バスケW杯】豪州戦も守備で相手を“イラつかせる”ことが大事
[ 2023年8月29日 04:44 ] バスケット
-

北口金メダルの立役者 セケラク・コーチにご褒美「ハイチュウ」を!森永製菓で計画進行中
[ 2023年8月29日 04:43 ] 陸上
-

錦織 全米OP欠場 左膝回復間に合わず「悔しい決断になりました」
[ 2023年8月29日 04:42 ] テニス
-

優勝はネット71・海野幸一さん 「スポニチ軽井沢72ゴルフチャレンジ」8月予選
[ 2023年8月29日 04:30 ] ゴルフ
-

首位はネット217・2の高橋英明さん 108ホールチャレンジゴルフ
[ 2023年8月29日 04:30 ] ゴルフ