大迫傑、反骨心育てた“大迫ロード” 毎週水曜日は上級生に「仕掛ける日」
2020 THE STORY 飛躍の秘密
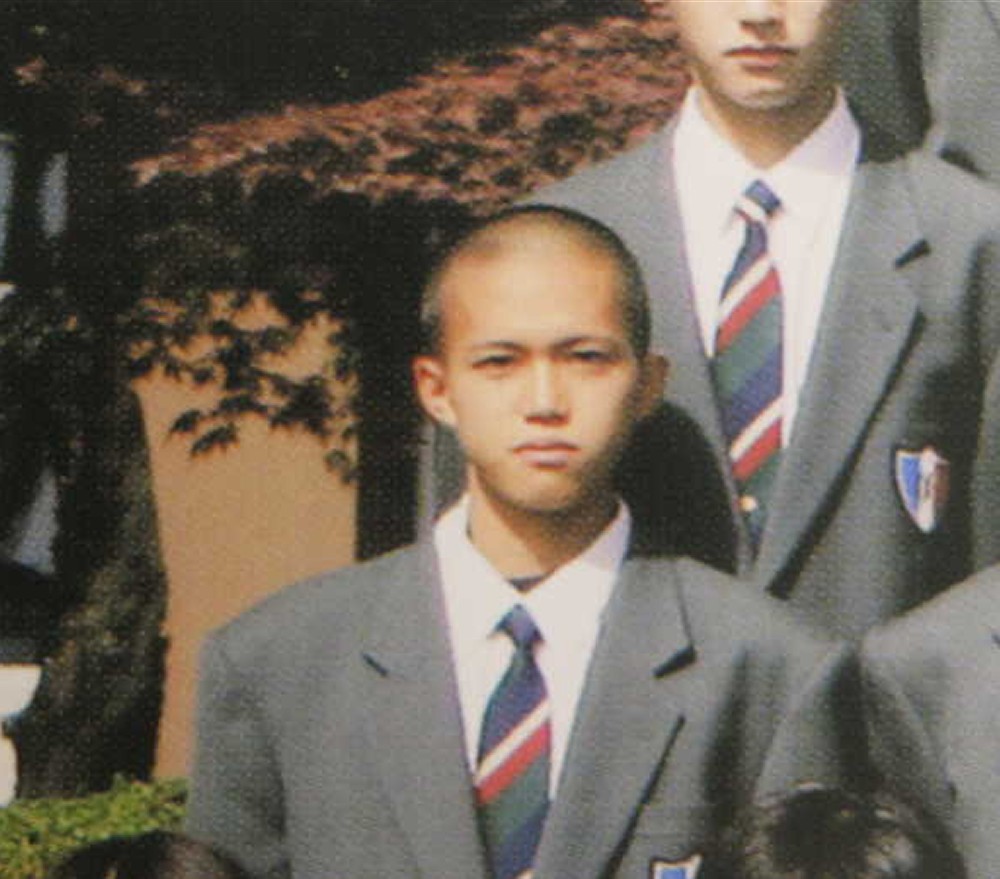
Photo By 提供写真
マラソンデビューから走るたびに日本中に衝撃を与え続けているのが大迫傑(27=ナイキ)だ。初挑戦から3戦目で2時間5分50秒の日本記録樹立という“半端ない”結果を出すまでの過程で、忘れてはいけないのが長野での高校時代だ。今では考えられないくらい負けまくり、悔しさを味わい続けた。臥薪嘗胆(がしんしょうたん)。高校での練習が快挙への大きな礎となっていた。
◆15歳で虎の穴
標高700メートル。寒暖差も激しく、冬季には氷点下10度以下にもなる長野県佐久市。この地に校舎を構える高校長距離界の名門・佐久長聖高で日本男子マラソン界の至宝は3年間、実力を磨いた。高校2年時には全国高校駅伝制覇の原動力になった大迫は、いかにして長野で成長したのか。
東京都町田市立金井中で全国大会3000メートル3位の活躍が目にとまり、佐久長聖高からスカウトされた。母親と学校見学に訪れた帰りの新幹線の中で「ここに決める」と即決。まだあどけなさも残る15歳は親元を離れ単身、年代トップの選手が集まる“虎の穴”で鍛錬することを選んだ。
1年目は全国高校駅伝不出場。1つ上の学年に村沢明伸(27=日清食品グループ)や佐々木寛文(28=プレス工業)ら強い上級生がいたこともあって、存在感はあまりなかったという。長野県代表として大迫とともに国体に出場、早大の同期で元110メートル障害選手の早川恭平教諭(現陸上部顧問)も「県内ではそんなに印象はなかったですね。やはり1つ上の学年が強烈すぎました」と振り返る。
実力開花の誘因となったのは上級生との“朝練バトル”だった。「先輩たちに挑んでいくのが大迫」。そう語るのは、当時の大迫をコーチとして支えた高見沢勝監督(37)。現在では交通事情などでクロカンコースでの練習に変わっているが、大迫が在籍していた時は月〜土曜日まで朝のロードワークが日課になっていた。
◆朝練でバトル
高低差に富む佐久市内を、日替わりルートでジョグしていた。しかし、毎週水曜日になると各選手の目の色が変わったという。理由は大迫が上級生相手に「仕掛ける日」だったから。選手たちはその日になるとレースシューズに履き替えるほど緊張感が増した。人数の関係で先発組、後発組に分かれて出発するが、大迫はいつも後発組に入った。すると上級生も大迫をつぶそうと、わざと後発チームに入ってスタートしたという。
2つのアップダウンを乗り越える約6キロの水曜日のコースの特徴は、上信越道脇の側道から高速道路の高さを上回るところまで一気に駆け上がる「佐久の壁」があること。大迫は毎回のように“壁”の手前から村沢に勝負を挑み、最後にはつかまってつぶされる。その繰り返しだった。卒業まで勝つことはなかった。「2度目の上りで必ず仕掛けて、先輩がねじ伏せる。負けてもどうにかして勝とうと次も挑んでいく」と高見沢監督。毎週毎週挑み続け、踏みつぶされ、それでもまたはい上がった。反骨心こそが大迫の力を育んでいった。
大迫が卒業した10年で、朝のロードワークは終了。ただ、高見沢監督は「現役にも走らせたいと思うほどの、いいコースなんです。いまでは走らないので“伝説の大迫ロード”になってますよね」と笑う。
◆「一番」に強いこだわり
厳しい練習が基礎を形づくっていたが、それに耐えうるメンタルの強さもすでに高校時代には出来上がっていた。佐久長聖高校駅伝部の監督を務めていた両角速監督(現東海大監督)は「当時も今も変わらないのは目つき。負けたくないというのは、一生変わらないと思う。将来的には“世界”と言っていた」と印象を語る。
2年で全国高校駅伝を制した大迫は、その後故障に悩んでいた。アキレス腱痛で満足な練習ができず、09年近畿インターハイでは1500メートル、5000メートルともに14位。そのレース中、スタンドにいた陸上関係者から「大迫も終わったな〜」などという声もささやかれたほどだった。
そこでくじけないのが、大迫たるゆえんだ。練習できないと体重が増えるからと食事では米を徹底的に抜いていたという。糖質制限は食べ盛りの高校生にとってはかなりタフな節制方法。かえって甘いものに走ったり、イライラしたりと難しい面もあるが、大迫はやってのけた。やり過ぎというくらいに自分を追い込んで、臨んだ3年時の都大路では1区で区間賞を獲得。高見沢監督は「スカッとしましたね。僕自身も悔しかったし、彼も悔しかったと思う。彼自身が逆境をエネルギーに変えたんだと思う」と愛弟子の成長に目を細めた。
◆下駄箱も食事も風呂も
寮生活でもトップへのこだわりは半端なかった。大迫の3年時にJR岩村田駅からほど近い場所に、会社の事務所を改修した駅伝部寮「聖徳館南館」が完成した。引っ越し当日。大迫が玄関で真っ先に「1番」の下駄箱をキープしたことは駅伝部では語り草になっている。
高校の授業が終わると真っ先に帰寮。練習に向かうのはもちろん一番で、そこからの帰寮もトップ。寮監として寝食を共にしていた高見沢監督は「夕飯を食べ始めるのも一番だから食べ終わるのも一番。当然のように風呂だって一番風呂になるんですよね。狙っているわけではないと思いますが、全てが素早いのでそうなっているんです」。一番へのこだわりは自然と植え付けられていった。
日本記録を3レース目で叩き出したが、常に一番を目指していた男にとって、足りないのはマラソンのタイトル。しかし、大迫を知る人たちの言葉からは不思議と「あいつならいける」と楽観視ともとれる期待の言葉が聞かれる。まずは19年9月の東京五輪マラソン代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」で代表権を勝ち取ることが目下の目標。四谷の坂も、佐久の壁に比べたらなんてことはない。真っ先にゴールラインを切る姿を佐久の恩人たちはイメージしている。
《忘れられない一本の電話》 大迫が佐久長聖高に入学してから3年間、クラス担任を務めた小平一教諭は「心の強さは入学したときから感じていた。それは3年間変わりませんでしたね」と当時を懐かしそうに振り返る。
陸上を志して入学した大迫が、確固たる信念を秘めていたことを感じ取っていた。「休み時間もあまり群れなかったですね。ホームルームが終わると練習にパッと出て行く。やはり陸上第一だったんでしょうね」
小平教諭には忘れられないシーンがある。大迫が高校2年時の全国高校駅伝。アンカーの大迫が優勝のゴールテープを切る歴史的な大会を、小平教諭は指導する剣道部のメンバーと京都で応援した。雨が降り、競技場トラックに入ってくる西京極公園内の石畳はスリップの危険があった。「“濡れてるから転ぶなよー”と叫んでましたね」
優勝を決めたその日の夜、長野に帰っていた小平教諭の元に大迫から一本の電話があったという。「帰校してからあいさつに来る生徒はいましたけど、電話で謝意を伝えてきたのは後にも先にも大迫だけだったんです。声掛けに対するありがとうだったのかな、今になればね」。教え子の意外なエピソードを思い出し、自然と相好を崩した。
《早大恩師「50年に一人」》 早大時代の恩師、渡辺康幸監督(現住友電工監督)は「瀬古利彦さんが100年に一人の逸材なら、僕の中では50年に一人の逸材」と愛弟子を評した。大迫が入学した年に早大は大学駅伝3冠を達成。その原動力になった大迫は、駅伝デビューとなった出雲で浮かない顔だったという。チームは優勝したものの「区間賞を獲れなかったのでむくれて全然喜んでなかった。負けることに納得がいかないやつだった」と逸話を明かした。
2018年11月28日のニュース
-

“次世代セクシー・クイーン”ユ・ヒョンジュ スコア伸ばせず27位に後退
[ 2018年11月28日 22:54 ] ゴルフ
-

“黄金世代”三浦桃香 72で18位に後退
[ 2018年11月28日 20:35 ] ゴルフ
-

原江里菜 ノーボギーの67で3位浮上 ゴルフやめようかと悩んだ時も…「しがみつくつもりで」
[ 2018年11月28日 19:50 ] ゴルフ
-

アン・シネ セクシー路線封印で69と逆襲、55位浮上
[ 2018年11月28日 19:33 ] ゴルフ
-

ラプターズが6連勝 グリズリーズは逆転負け ナゲッツはレイカーズに圧勝
[ 2018年11月28日 15:01 ] バスケット
-

Gリーグ・ハッスルの渡辺雄太が自己最多の12リバウンド チームは接戦を制して5勝目
[ 2018年11月28日 13:13 ] バスケット
-

大迫傑、反骨心育てた“大迫ロード” 毎週水曜日は上級生に「仕掛ける日」
[ 2018年11月28日 11:30 ] 陸上
-

元貴親方、改めて「卒婚」を強調「夫婦としての成り立ちを良い思い出に」
[ 2018年11月28日 06:07 ] 相撲
-

紀平「昼寝」でザギトワ撃破だ!GPファイナルV誓う
[ 2018年11月28日 05:30 ] フィギュアスケート
-

フランス杯準Vの三原 “学生の本分”も頑張る
[ 2018年11月28日 05:30 ] フィギュアスケート
-

イ・ボミ、イケメン俳優と熱愛 韓国複数メディア報じる
[ 2018年11月28日 05:30 ] ゴルフ
-

ユ・ヒョンジュが最終予選会参戦 “新セクシー・クイーン”「日本で頑張りたい」
[ 2018年11月28日 05:30 ] ゴルフ
-

“黄金世代”が好スタート 三浦ホッ「凄い不安だった」
[ 2018年11月28日 05:30 ] ゴルフ
-

奈紗、フロリダに家買う!米国に拠点「今年中には見つけたい」
[ 2018年11月28日 05:30 ] ゴルフ
-

ジョセフHC、W杯へ選手層増強 主力と控え「並行して強化する」
[ 2018年11月28日 05:30 ] ラグビー
-

駒大陸上部監督がパワハラ告発 大学側は金銭問題あると主張 第三者委員会設置へ
[ 2018年11月28日 05:30 ] 陸上
-

青学大に弱点なし 対抗に東洋大、東海大 箱根駅伝シンポジウムで展望
[ 2018年11月28日 05:30 ] 陸上
-

体操・宮地が帰国 コトブス国際3位に「納得いく試合だった」
[ 2018年11月28日 05:30 ] 体操
-

ロンドン銀のフジカキ組が本戦進出 今季限りで引退
[ 2018年11月28日 05:30 ] バドミントン
-

スポーツクライミング野口、Qちゃん&伊達から金言 世界選手権に照準
[ 2018年11月28日 05:30 ] スポーツクライミング
-

元貴親方、景子さんの芸能活動意欲に不満 今年夏頃に噴出…離婚一因に
[ 2018年11月28日 04:00 ] 相撲




















