【コラム】金子達仁
攻撃の幅広げた最終ラインからのパス
国際親善試合 日本2-0エルサルバドル ( 2019年6月9日 ひとめS )

Photo By スポニチ
想像するに、この試合でもっとも手応えをつかんだのは最終ラインの3人ではなかったか。
トリニダード・トバゴ戦では、破綻はなかったものの、機能したとも言い難かった。だが、より攻撃的な選手が中盤の両サイドに配置されたこの日、冨安や畠中はその利点を極めて効果的に運用した。つまり、スピードのある選手がサイドに張ったことで、エルサルバドルは中央部を固めるわけにはいかなくなった。結果、以前よりは低くなった人口密度を、日本の最終ラインは縦パスという形で利用したのである。
紆余(うよ)曲折はあったものの、ここのところボールポゼッション重視のスタンスが続いてきた日本サッカーだが、こと日本代表に関する限り、最終ラインからのフィード力が武器になったことはほとんどなかった。森保体制で臨んだアジア杯でさえ、パスではなくキックに逃げてばかりの試合があった。DFは、セットプレー以外は専守防衛。それが日本代表の現実だった。
だが、この日のように最終ラインからのパスが得点に直結するようになれば、攻撃のバリエーションは飛躍的に広がる。人間の集中力には限界がある。最終ラインからのパスを警戒せざるをえなくなる相手には、いずれ中盤や前線のケアを疎(おろそ)かにする瞬間が生まれるからだ。
この日の森保監督は試合途中で3バックを4バックに変えた。だが、実際にW杯予選などで運用されるのはこの逆のパターンではないか、という気もする。4バックで臨んで攻めあぐんだ。3バックにして両サイドを張り出させ、この日の前半と似たような状況を作り出す――。
もちろん、まだまだ粗い面も目立ち、効果的な武器として使えるようになるにはさらなる経験値の上乗せが必要だが、最終ラインだけでなく、森保監督にとっても、次のステップに進めるという手応えの得られた試合ではなかったか。
収穫の多かった試合の中で、唯一気になったのが堂安。それぞれが新しいやり方の中で自分の立ち位置を見つけつつある中、彼だけが居場所を見つけられずにもがいているような印象を持った。右サイドからカットインしての左インフロント、という“必殺技”も封印されたままだった。同じ左利きの強烈なライバルの出現が、彼にポジティブな化学反応を引き起こしてくれればいいのだが。
さて、久保建英である。おそらく、スポニチだけでなく、各紙、各メディアも彼のデビューを大きく取り上げるはず。歴代2位の若さでの初キャップとのことだが、おそらく、1位の市川大祐さんは苦笑しているのではないか。注目度も、期待度も、そしてチーム内における立場も、市川さんの時とは比較にもならないぐらい上だからである。
ただ、いいパスがあった、惜しいシュートがあった、落ち着いてプレーしていた、だから素晴らしかったと言われているうちの久保は、まだ本物ではない。同じことをメッシがやったら、「でも決めなかった」と批判される。久保は、そういう位置を目指せる、いや、目指さなければならない選手である。(金子達仁氏=スポーツライター)
バックナンバー
-

苦さが残るU-23GK小久保の極端な時間稼ぎ
[ 2024年4月18日 10:00 ] サッカー
-

41歳川島の存在感が磐田に与えるプラス効果
[ 2024年4月5日 17:30 ] サッカー
-

もし自分が、水原通訳の立場だったなら…
[ 2024年3月28日 21:30 ] サッカー
-

このサッカーが続くなら――もう日本代表に期待はできない
[ 2024年3月22日 04:50 ] サッカー
-

伊東の疑惑が晴れた時、協会は特別な対応が必要
[ 2024年3月21日 07:00 ] サッカー
-

森保監督が守田に直接問うべき「指示して」発言の真意
[ 2024年3月14日 07:00 ] サッカー
-

町田は荒々しく挑戦的な「メタル・フットボール」
[ 2024年3月7日 11:00 ] サッカー
-

女子サッカーが“滅びる”恐怖に打ち勝った
[ 2024年2月29日 12:00 ] サッカー
-

なでしこに得策ではない北朝鮮との憤りぶつけあい
[ 2024年2月22日 10:00 ] サッカー
-

森保体制でファンの不満鎮めるカギは川崎F?
[ 2024年2月15日 04:50 ] サッカー
-

それでも森保監督で行くべきか迷う
[ 2024年2月8日 04:50 ] サッカー
-

生まれ変わった姿を見せなければ鈴木彩艶に代表の資格なし
[ 2024年2月5日 04:30 ] サッカー
-

それでも彩艶には、とてつもないポテンシャルがある
[ 2024年2月2日 04:50 ] サッカー
-

「見られること」でアジアのサッカーは進歩する
[ 2024年2月1日 17:00 ] サッカー
-

2戦4失点・・・GKの“自責率”は?
[ 2024年1月25日 04:40 ] サッカー
-

敗因は個々の能力への過信と裏目に出た監督采配
[ 2024年1月21日 14:00 ] サッカー
-

頬、緩む サッカー日本代表・細谷が味わった幸運な屈辱
[ 2024年1月18日 04:50 ] サッカー
-

退屈なプレー許さない環境つくれるか
[ 2024年1月5日 06:00 ] サッカー
-

大谷、尚弥が“変えた”勝利に驚かないメンタル
[ 2024年1月1日 10:30 ] サッカー
-

J秋春制移行 降雪地クラブへ国、自治体も支援を
[ 2023年12月21日 06:00 ] サッカー
-

森保ジャパンの長く感じた2023年の流れに感謝
[ 2023年12月19日 19:00 ] サッカー
-

日本は平均値維持し、個も育てる方法模索を
[ 2023年12月7日 06:00 ] サッカー
-

評価したい日本選手の必死さ
[ 2023年11月17日 06:00 ] サッカー
-

監督人選に独自色の町田、南葛…フロントに存在感
[ 2023年11月9日 06:00 ] サッカー
-

「礼節」こだわらず「衣食」求めたなでしこ
[ 2023年11月7日 18:30 ] サッカー
-

町田・黒田監督が新たに開いた日本特有の道
[ 2023年10月26日 06:00 ] サッカー
-

自分たちの成長と現在地を認識できた
[ 2023年10月19日 08:00 ] サッカー
-

古橋の高い意識を証明したQBK弾
[ 2023年10月19日 05:00 ] サッカー
-

カナダ人の深層心理に強敵と刷り込めた
[ 2023年10月14日 06:30 ] サッカー
-

許されない…競技を汚した“北の蛮行”
[ 2023年10月5日 11:30 ] サッカー
-

W杯優勝…その前にきっと立ちはだかる“あと1里の壁” 今の日本サッカーに満足するのは早い
[ 2023年9月28日 06:30 ] サッカー
-

暴徒化ファンにあえてできることを探すなら…選手の介入だろうか
[ 2023年9月21日 06:30 ] サッカー
-

日本サッカーは明治期の日本と似た道を進んでいる ただ、過信も驕りも禁物
[ 2023年9月14日 06:00 ] サッカー
-

ドイツ完敗もやむなし… これは日本サッカー界の精神構造をも変える大きな勝利
[ 2023年9月11日 06:00 ] サッカー
-

バスケW杯の熱狂「スポーツ」より「日本」を楽しんでいませんか?
[ 2023年9月7日 21:00 ] サッカー
-

女子サッカー人気に必要な“新アイデア”
[ 2023年8月31日 17:00 ] サッカー
-

2年ごとの女子W杯開催考えてもいい
[ 2023年8月26日 10:00 ] サッカー
-

【女子W杯】スペイン 決勝に進出してもなお残る日本戦大敗へのうずき これぞサッカーの魅力
[ 2023年8月17日 06:00 ] サッカー
-

【女子W杯】なでしこにとっての“ドーハの悲劇” だからこそ、この敗北は未来につながる血の涙
[ 2023年8月12日 10:00 ] サッカー
-

スペイン戦の経験は、この先なでしこの支えになる
[ 2023年8月3日 06:00 ] サッカー
-

どんな試合でも望む“なでしこ”らしい戦い
[ 2023年7月28日 09:00 ] サッカー
-

ゼロを1にする天皇杯の番狂わせ
[ 2023年7月22日 14:00 ] サッカー
-

地上波放送なくとも 勝てば何かが変わる
[ 2023年7月14日 06:00 ] サッカー
-

「蹴球」から「足球」へ U―17日本代表に見た日本の進化
[ 2023年7月6日 10:00 ] サッカー
-

日本サッカー界の成熟を見たU―17日本代表への熱量
[ 2023年6月29日 10:00 ] サッカー
-

責任を問うのはあまりにも酷… 韓国・クリンスマン監督の苦悩
[ 2023年6月22日 10:00 ] サッカー
-

日本はFIFAランク10位から20位前後でチート級の強さ…そんな気にさせられた
[ 2023年6月21日 10:00 ] サッカー
-

ストライカーの“ズラタン化”必須
[ 2023年6月16日 11:00 ] サッカー
-

意外だった堂安の背番「10」に対する気概
[ 2023年6月15日 13:30 ] サッカー
-

選手発掘へ スポーツ界全体でも求む“現役ドラフト”
[ 2023年6月10日 07:00 ] サッカー
-

U20日本代表は「劇薬」に手を出す段階ではなかった
[ 2023年6月5日 11:00 ] サッカー
-

Jリーグに欠けているオランダ的な発想
[ 2023年5月25日 08:00 ] サッカー
-
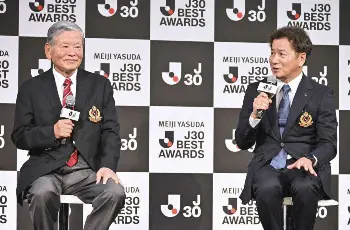
「外国人選手と審判」の関係も30年で大きく進歩
[ 2023年5月18日 22:00 ] サッカー
-

Jに“波及効果”なければACLさらに厳しく
[ 2023年5月13日 06:00 ] サッカー
-

アルヒラルの“本来の姿”埼スタで牙をむく
[ 2023年5月5日 20:00 ] サッカー
-

冷ややかな眼差しが誹謗中傷を減らす?
[ 2023年4月30日 13:00 ] サッカー
-

世界の強豪クラブの「敵陣保持率」からもヒントを
[ 2023年4月22日 10:00 ] サッカー
-
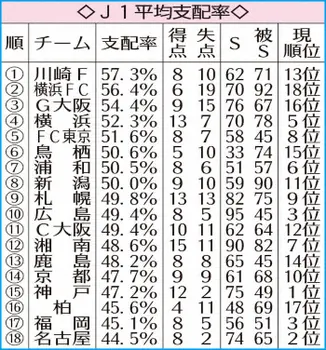
気になる日本の敵陣での保持率
[ 2023年4月14日 11:00 ] サッカー
-

指先1本でチームに打撃… 嫌な時代
[ 2023年4月11日 13:00 ] サッカー
-

満員の敵地で欧州勢とテストマッチを
[ 2023年4月4日 10:00 ] サッカー
-

「上田の高さ」生かせず 欠如していた集団としての知恵
[ 2023年3月30日 06:00 ] サッカー
-

世界一になるために前に 運ぶという「習慣」と「意志の力」を
[ 2023年3月26日 06:00 ] サッカー
-

W杯並み熱気が米国をWBCに引き寄せた
[ 2023年3月10日 12:10 ] サッカー
-

町田・黒田監督の言葉でJ2に新しい風吹くか
[ 2023年3月3日 11:00 ] サッカー
-

敗れてもスタイルぶれない川崎F軸
[ 2023年2月25日 09:45 ] サッカー
-

“孫正義さん”になれなかったJのギャラ
[ 2023年2月18日 10:00 ] サッカー
-

日本のサッカー観を変える三笘のドリブル
[ 2023年2月10日 07:00 ] サッカー
-

歴史に刻まれる久保、三笘の活躍ぶり
[ 2023年2月2日 11:30 ] サッカー
-

欧州3大リーグ日本人監督誕生へ 本田圭佑に“期待”
[ 2023年1月31日 12:40 ] サッカー
-

森保監督の新しい「懐刀」は名波氏か前田氏か?
[ 2023年1月20日 07:00 ] サッカー
-

久々の“キャッチするGK”岡山学芸館・平塚 今後に期待
[ 2023年1月14日 14:00 ] サッカー
-

覚醒した“日本のネイマール”三笘に日本の未来を見る
[ 2023年1月6日 06:00 ] サッカー
-

オーラ放つこと拒絶した「王様」 こんな人は二度と現れない
[ 2022年12月31日 10:00 ] サッカー
-

16強の壁打破へ…鎌田、久保、南野不発の原因検証を
[ 2022年12月30日 14:00 ] サッカー
-

エムバペ筆頭にアスリート化で11人駿足の時代に?
[ 2022年12月25日 08:00 ] サッカー
-

神になることを拒んだ男 メッシの壮大な英雄伝
[ 2022年12月21日 12:00 ] サッカー
-

代表チームの強さと人口は無関係である
[ 2022年12月19日 17:00 ] サッカー
-

世界に変革促したモロッコの勇気と躍進
[ 2022年12月16日 10:00 ] サッカー
-

メッシは母国の新たな「神」になれるか
[ 2022年12月15日 10:00 ] サッカー
-

モロッコ躍進は就任3カ月の監督の手腕?ハリル監督更迭後に就任
[ 2022年12月8日 11:40 ] サッカー
-

Jリーグの発展こそが“6・7キロの差”埋める礎となる
[ 2022年12月7日 07:00 ] サッカー
-

名声得た森保監督続投を支持しない理由
[ 2022年12月6日 11:00 ] サッカー
-

W杯を「変えた」アジア、アフリカ 支配者たちを“臆病”にさせたアウトサイダー快進撃の連係
[ 2022年12月5日 11:00 ] サッカー
-

一つの試合でドイツは変わった 日本もきっと…
[ 2022年12月4日 11:00 ] サッカー
-

森保ジャパンに見た勇気と決断力 「ジョホールバルの夜」を超えた伝説の夜
[ 2022年12月3日 12:00 ] サッカー
-

もう欧州や南米だけの時代ではない。アジアも、世界だ
[ 2022年12月2日 20:30 ] サッカー
-

“反ルイス・エンリケ” スペイン・マルカ紙の報道は信じるべきか
[ 2022年12月1日 08:00 ] サッカー
-

計算された怒り?監督とは役者である
[ 2022年11月30日 08:00 ] サッカー
-

選手たちよ「憂いるな」挑戦者として戦うのみ
[ 2022年11月29日 17:00 ] サッカー
-

“超消極的”にお付き合い…前半をドブに捨ててしまった
[ 2022年11月29日 00:00 ] サッカー
-

世界のサッカー史に残る 3%の奇跡的逆転勝利
[ 2022年11月25日 11:00 ] サッカー
-

アルゼンチンを呑み込んだサウジの“2つの罠”
[ 2022年11月24日 11:00 ] サッカー
-

斬新なGK起用で得られる果実 森保監督はどうする?
[ 2022年11月23日 06:00 ] サッカー
-

考えを変えた 滅多に起こらないことが起きた大会では滅多に起こらない結果残る
[ 2022年11月21日 22:30 ] サッカー
-

セットプレーとセットプレーからのカウンター。封印を解き放つ時
[ 2022年11月19日 04:30 ] サッカー
-

“4年前ベルギー戦の悪夢”再び体感した麻也に油断なし?
[ 2022年11月17日 10:00 ] サッカー
-

8強「以上」目標ゆえの大迫選外か
[ 2022年11月4日 11:00 ] サッカー
-

チームの骨格が見える今回の代表選考
[ 2022年10月28日 09:00 ] サッカー
-

W杯でも見たい箱根流「関東学連選抜」
[ 2022年10月25日 12:00 ] サッカー
-

青森山田高・黒田監督に越えてもらいたい“プロの壁”
[ 2022年10月14日 07:00 ] サッカー
