「バイプレイヤーズ」大杉漣 脇役の極意「全然ない」模索し続ける“表現の沼”
「バイプレイヤーズ」名脇役インタビュー(最終回)大杉漣(上)

Photo By 提供写真
俳優の大杉漣(65)が、日本映画界に不可欠な名脇役6人による夢の共演で話題を呼ぶテレビ東京「バイプレイヤーズ〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜」(金曜深夜0・12)を最年長として引っ張っている。“おじさんたちの部活・合宿”と呼んだ約1カ月半の撮影を終え、安堵感とともに「みんなに会えない」と寂しさも吐露。脇役を演じる極意について尋ねると「全然ないですよ〜」と苦笑い。百戦錬磨の大杉をして、芝居は底の見えない、今なお模索し続ける“表現の沼”。その深淵さが垣間見えた。
大杉とともに、遠藤憲一(55)田口トモロヲ(59)寺島進(53)松重豊(54)光石研(55)=アイウエオ順=の6人が“主演”。全員が本人役に扮し、共同生活を送るというストーリーの異色作。中国の動画配信サイトから映画「七人の侍」リメークのオファーを受けた6人は絆を深めるため、シェアハウスで3カ月、一緒に暮らすことに。“おじさんだらけのテラスハウス”の行方、そして10年前に撮影しながら頓挫した6人による映画「バイプレイヤーズ」はどうなるのか…。
昨年12月21日にクランクイン。シェアハウスのシーンは千葉・館山で撮影を行い、今月6日にクランクアップ。大杉は「かなりタイトなスケジュールだったんですが、疾風のごとく走り抜けたという感じでしょうか。若い人とは違うかもしれないですが、おじさんにはおじさんなりの走り方がありまして。僕たちなりの現場への向かい方を貫けたと思います。ホッとしたという安堵感と、もうみんなに会えないんだという寂しさと…それぐらい濃密な時間だったものですから、両方の気持ちがあります」と振り返った。
6人を特集した2002年秋の映画祭「6人の男たちフィルムズ」(東京・下北沢)から、10年後の雑誌対談を経て、14年越しで実現した奇跡の共演。「ドリマックスさん、テレビ東京さん、よくぞ今回の企画を立ち上げてくださいました。これがなければ、6人の新しい出会いはなかったものですから」と感謝した。
精力的な仕事ぶりから“300の顔を持つ男”の異名を取ったバイプレイヤーの代表格。脇役を演じる秘訣は?と水を向けると「全然ないですよ〜」と苦笑いしながらも、約45年のキャリアを積んで到達した境地を明かした。
「自分の人生をどう生きるかということと役者は非常につながっているという考え方をしているものですから、セリフ1つにしても、こいつは普段どういう生き方をし、どういうふうに日々を過ごしているのかということが写し鏡のように出てくる。それが演技という作業だと思っています。65歳になっても、こんなにフワフワしていて、今まで自分の中で“これでよし”なんていう確信めいた答えがあったかどうか、分かりません。本当に一生懸命、1本1本の作品とちゃんと向き合うことしかなかったと思います」
小津安二郎監督の「東京物語」「秋刀魚の味」などで日本映画史に刻まれる名優・笠智衆さんの著書「あるがままに」(1992年刊)に感銘を受け、座右の銘は「あるがままに」。笠さんは「この本のタイトルは『あるがままに』というのですけれど、何をやっても“自然体”に見える――これは、僕がずっと心がけてきたことです」と記している。大杉も「その瞬間のリアリティーを感じていたい」という。「僕はまだまだ駆け出しのようなところがありますが…」と前置きしながら、滔々(とうとう)と言葉を紡ぐ。
「やっぱり表現って、どこに行っていいか分からない世界なんだと思うんです。僕はよく“表現の沼”とか“表現の海”とか言うんですが、昔は演技がおもしろいかどうか分からず、その水たまりの中に足首が浸かり、膝が浸かり、腰が浸かり、今は全身が浸かっているのかもしれないですが、それでも、さっき申し上げた自分なりの走り方じゃないですが、それができれば、たまにはプカッと浮いてみたりですね。今の世の中、割とハッキリ白黒つけないといけないみたいな風潮がありますが、特にインターネットの世界はすぐに答えが分かるような世界じゃないですか。ただ、僕らの世界はクリックしてもクリックしても次の課題が出てきて。クリックというのも変ですが、現場、現場という意味合いでしょうか。クリックしてもクリックしても、現場を経験しても経験しても行き着くところはないんですね。この世界に身を置いている宿命と申しましょうか。“これだ”というものを見つけられたとしても、ある日、急にそれが指の間からこぼれ落ちるような世界ですから。だから1本1本の作品にきちんと向き合って、やっていくしかないんだと思います」
2017年2月24日のニュース
-

モー娘。佐藤優樹が活動再開へ 腰椎椎間板ヘルニアで休養中
[ 2017年2月25日 00:22 ] 芸能
-

TBS山本アナ&元乃木坂46市来 社交ダンスペア解消 その理由は…
[ 2017年2月24日 22:57 ] 芸能
-

エビ中ラジオ、松野さん“出演せず” 真山りか単独で進行、ゲスト歌手と対談
[ 2017年2月24日 22:10 ] 芸能
-

NHK上方漫才コンテスト ゆりやんレトリィバァが優勝「サンキュウー」
[ 2017年2月24日 21:44 ] 芸能
-

小沢健二「フジロック出ます」 20年ぶり出演Mステでサプライズ発表!弘中アナもビックリ
[ 2017年2月24日 20:45 ] 芸能
-

トシちゃん告白 1月に明菜から電話「トシ元気?いつも見てるから…」
[ 2017年2月24日 20:21 ] 芸能
-

オリラジ中田自画自賛?再ブレイクは「本当に才能がないと難しい」
[ 2017年2月24日 20:04 ] 芸能
-

小沢健二、20年ぶりMステ出演 OPであいさつ「前世に帰ってきたみたい」
[ 2017年2月24日 20:02 ] 芸能
-

フジテレビ社長 月9苦戦に現場を鼓舞、大多常務は「一つの波の中にある」
[ 2017年2月24日 16:33 ] 芸能
-

海老蔵 新居探しの理由は麻央「やっぱり一番」「子供部屋も必要」
[ 2017年2月24日 14:35 ] 芸能
-

出川哲朗 ゴールデンで初の冠番組「タモリさんをぶっ倒します」
[ 2017年2月24日 13:59 ] 芸能
-

海老蔵 家族4人の食事に「感動」麻央観劇舞台 濡れ場は控えめ
[ 2017年2月24日 13:40 ] 芸能
-

橋本マナミ 恋愛はご無沙汰 実は「スキャンダル1回もない」
[ 2017年2月24日 11:16 ] 芸能
-

「キャプテン」復活 再現される故ちばあきお氏の“線”と“心”
[ 2017年2月24日 10:30 ] 芸能
-

サンシャイン池崎の“空前絶後”な父 タバコ不始末で実家工場2度全焼
[ 2017年2月24日 09:00 ] 芸能
-

文枝芸能50周年 モメる鶴瓶&さんまを横目に「見抜いた僕は偉かった」
[ 2017年2月24日 08:52 ] 芸能
-

村上春樹氏4年ぶり長編「騎士団長殺し」発売 ファン「冒頭から引き込まれる」
[ 2017年2月24日 08:41 ] 芸能
-

清水富美加はまるでお手本のような出家をしたなあ
[ 2017年2月24日 08:00 ] 芸能
-

「バイプレイヤーズ」大杉漣 脇役の極意「全然ない」模索し続ける“表現の沼”
[ 2017年2月24日 07:30 ] 芸能
-

大杉漣 65歳でも「右往左往」不安を力に探求の日々「俳優に正解ない」
[ 2017年2月24日 07:30 ] 芸能
-

ベッキー3・4「神戸コレクション」初出演
[ 2017年2月24日 06:30 ] 芸能
-
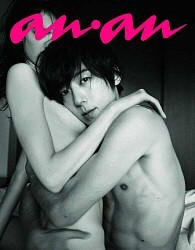
高橋一生ヌードグラビア初挑戦「誰かの肩に触れるだけでも…」
[ 2017年2月24日 06:30 ] 芸能
-

波瑠4月クールで初の不倫ドラマ 「忘れられない人」と禁断の愛
[ 2017年2月24日 06:00 ] 芸能
-

富美加 ベッキー騒動でLINE“封印”?「怖くなって」
[ 2017年2月24日 05:40 ] 芸能
-

観月ありさ26年連続で連ドラ主演決定 骨が好きな“変人”役
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

沢尻エリカ念願アクション 初刑事役で松坂桃李と対決
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

鳥羽一郎“おやじ”で師匠に別れ「一緒に歌っていきます」
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

GACKT円形脱毛症「格付けチェック」収録後見つかる
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

YOSHIKI ToshIに…洗脳を相談!?
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

ロッチ頂点も自虐「ブルゾンが優勝した方が…」
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

佐藤勝利&橋本環奈 吹奏楽部員らと合奏「泣きそう」
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

さしこSTU劇場支配人兼任 岡田奈々が“船長”に
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

NMB市川美織 鳳恵弥と母子役に「運命」感じた
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

こぶしファクトリー 鬼教官ベッキーは「プライベートだと…」
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能
-

相武紗季おノロけ新婚生活「胃袋つかめてたらいいな」
[ 2017年2月24日 05:30 ] 芸能

























