「真田丸」三谷脚本はどう作られた?行間が深いワケ…“参謀”が明かす秘密
真田丸特別連載(6)「創造」最終回まであと1日

Photo By 提供写真
ヒットメーカー・三谷幸喜氏(55)が12年ぶりにNHK大河ドラマの脚本を手掛けた「真田丸」(日曜後8・00)は18日、最終回を迎える。戦国時代最後の名将・真田幸村(堺雅人)の生涯を描く中、登場人物ぞれぞれの個性を際立たせ、数々の笑いや“仕掛け”を交える鮮やかな手腕がお茶の間を魅了した。三谷脚本はどのように作られたのか。その秘密に迫るべく、脚本作りに携わり“三谷氏の最も近くにいた”と言える制作統括の吉川邦夫チーフプロデューサーに聞いた。
◆「等身大の目線でリアルな人間として描きたい」三谷氏と時代考証の橋渡し
吉川氏は1985年入局。90年、ドラマ部に異動。2010年から2年間、放送文化研究所に籍を置いた以外はドラマ畑。もともとはディレクターで「真田丸」も第4話「挑戦」(1月31日放送)の演出を担当した。大河ドラマに関わるのは今回が7作目。
三谷氏が初の大河脚本を担当した「新選組!」(04年)からの付き合い。当初は2番手のディレクターを務める予定だったが、三谷氏との脚本作りを先行。「最後までのメドがついたら演出をしようと思っていたんですが、最終回の1つ前、第48話『流山』しか演出に割く時間が残っていませんでした」と苦笑いで振り返った。
三谷氏と吉川氏の関係は、言ってみれば作家と編集者。三谷氏の“最初の相談相手”で、三谷氏のアイデアを聞いて時代考証の学者(黒田基樹氏、平山優氏、丸島和洋氏)との橋渡し役も担う。「大河ドラマの場合、ストーリーは大きな流れが決まっていますが、三谷さんは常に等身大の目線でキャラクターを描きたい。あまり人物を定型にハメたくないんです。振れ幅の大きいリアルな人間として描きたいということがあるので、それをどうやって歴史上の出来事と結び付けていくか」がポイントの1つになった。
例えば、豊臣秀次(新納慎也)。謀反を企てたことを理由に豊臣秀吉から切腹を命じられた、という解釈が従来は主流だった。素行の悪さから「殺生関白」と呼ばれたという説もあるが、今回はそのような描き方をしなかった。秀吉は実の息子・拾(秀頼)を溺愛する一方で、甥の秀次にも目をかけ、気遣った。秀頼が成長するまで守ってくれる数少ない身内だったからだ。しかし、秀次はその気遣いの意図を読み違え、プレッシャーを感じて自らを追い込んだ…。
「三谷さんは秀次の哀しみを等身大で描きたいので『殺生関白』といった記号的に悪い人物にしたくないわけです。秀次が重圧に押しつぶされて自害したという説があると分かり『それは僕らが描きたかった秀次そのもの』と一連の流れが出来上がったんです」
◆長く書き→削り→再構築&凝縮 説明排除「テンポよくなり、行間深まる」
三谷氏の大河ドラマの“書き方”については、こう解説する。
「だいたい長く書かれます。それを削り、再構築し、凝縮していく。そうすると、人がAからCに変化する時、普通は変化するためのBというシーンがあるんですが、ポーンとなくなってしまうことがあります。一見すると感情が飛んでいるですが、飛ばすことによって、逆にその間にどういうふうに人が変わるのかというのを、視聴者の皆さんが想像することができる。ある意味、視聴者の皆さんを信じているとも言えますが、間を全部説明しようとしない。だからテンポが良くなる上に、行間がより深まって、話が盛り上がるんです。きり(長澤まさみ)はどうしてああいう行動をしたのか、春(松岡茉優)は一体どのような女性なのか、どういう家庭環境だったらああいう人物になるのか…と。三谷さんの中で、一度膨らませてから凝縮しているから、全部説明されなくても、実感が生まれるんです」
一例は第1話「船出」(1月10日放送)。武田家が絶体絶命の危機を迎え、囲炉裏を囲んだ真田家の“家族会議”。父・真田昌幸(草刈正雄)は一家全員を前に「安心せえ。この真田安房守がいる限り、武田が滅びることは決してない」。直後のシーン、息子の信幸(大泉洋)信繁(堺)と3人だけになると、昌幸は「武田は滅びるぞ」−。
「単純に見るとギャグのようにも思えるし、もちろん笑えるんですが、そこには行間が生まれていて。(昌幸の)母・とり(草笛光子)、妻・薫(高畑淳子)、娘・松(木村佳乃)と女たちの前だと『滅びない』と言い、息子2人の前だと『滅びる』と言う。その間に『昌幸がなぜそうするか』ということは全く語られていないわけですが、昌幸は息子2人を他の者とは全然違うふうに見ているということ、息子2人には本音を語るということが象徴されています。そして昌幸が、必要ならためらうことなく二枚舌を使う男だということも」
◆終盤の追い込み時“24時間態勢”の打ち合わせ 仮眠時も耳元に携帯電話
終盤の追い込み時は連日、電話とメールによる打ち合わせ。通常は顔を合わせてしていたが、三谷氏も執筆で缶詰め状態なら、吉川氏も準備稿の直しや先の展開の史料調べなどで缶詰め状態。24時間、お互いにいつ連絡を取りたくなるか分からないので、移動の時間がもったいなかった。仮眠を取る時も、電話やメールの着信に気づくように、耳元に携帯電話を置いて寝た。
「苦労がなかったとは言いません。50本は多いと、あらためて思いました」としながらも「多いからこそ、50回のドラマを最初から全部決めて作っていたら、ハッキリ言っておもしろくないんです。大河ドラマは30回台くらいに、書いている人も撮っている人も演じている人も疲れてしまい、中だるみすることがあるんですが、今回は全くそれがなかった。それは、三谷さんが物語の向かう先を決め決めにせず、柔軟に人物を動かしていったからだと思います。特に歴史物は出来事が決まっているから、つい枠にハメがちなんですが、定説を『本当にそうなのか?』と疑ってかかる余地、あるいは史料にあえて書かれていない部分に意外と大事な真実があるんじゃないかと想像を巡らせる余地を、常に三谷さんは残している。隙間を残しておくということは怖いんですが、それでこそ話が膨らむので」と三谷氏の作劇を絶賛。長い共同作業を終え、充実感がにじんだ。
2016年12月17日のニュース
-

「真田丸」異例ずくめの最終回 幸村の運命は…屋敷CP見どころ「想像つかない」
[ 2016年12月18日 05:00 ] 芸能
-

堺雅人「真田丸」幸村以外に演じたい役は?“無理”な役は?
[ 2016年12月18日 05:00 ] 芸能
-

香取慎吾スマステで明かす…山本耕史&堀北真希夫妻に第1子誕生
[ 2016年12月17日 23:38 ] 芸能
-

中居ラジオ新番組名 SMAPの名が外れる
[ 2016年12月17日 23:29 ] 芸能
-

小林麻央 今年の漢字は「苦」 「苦しみもがいた時も刻んでおこう」
[ 2016年12月17日 22:26 ] 芸能
-

ろくでなし子、妊娠していた「異常もなく8ケ月目」44歳、高齢出産について問題提起
[ 2016年12月17日 21:23 ] 芸能
-

「君の名は。」新記録 中国で「ドラえもん」抜く
[ 2016年12月17日 20:50 ] 芸能
-

島木譲二さん通夜 遺影はおなじみの灰皿手にファイティングポーズ
[ 2016年12月17日 19:52 ] 芸能
-

倉木麻衣「素敵な場所で、素敵な方と過ごすのは憧れます」
[ 2016年12月17日 19:42 ] 芸能
-

広田亮平&浦上晟周 「真田丸」父・幸村&信之への思い語る
[ 2016年12月17日 18:35 ] 芸能
-

武井咲「パンチが忘れられない」斎藤工「鼻から春雨が出るくらいだった」
[ 2016年12月17日 16:59 ] 芸能
-

西村雅彦、イベントで「黙れ小童!」連発!裏話も披露しファン大喜び
[ 2016年12月17日 16:01 ] 芸能
-

テレ東・鷲見玲奈アナ「ウイニング競馬」卒業を発表「お世話に」
[ 2016年12月17日 16:00 ] 芸能
-

間寛平、島木譲二さんを追悼 “カンカンヘッド”誕生秘話明かす
[ 2016年12月17日 15:14 ] 芸能
-

畑中葉子、伝説のセクシーソング披露 “攻めの3曲”で「どんどん攻めますよ〜」
[ 2016年12月17日 15:00 ] 芸能
-

磯山さやか 今年は「安」まわりは結婚 また自虐「あてはまったくない」
[ 2016年12月17日 14:57 ] 芸能
-

人間国宝・鶴澤寛治 体調不良で文楽公演休演
[ 2016年12月17日 14:34 ] 芸能
-

夏場の“パンイチ”草刈家では普通 紅蘭「私も下着で父の前を歩きます」
[ 2016年12月17日 14:26 ] 芸能
-

草刈正雄 極度のマイナス思考で「真田丸」見られない 長女・紅蘭が明かす
[ 2016年12月17日 13:58 ] 芸能
-

東出昌大 パパになって分かった親心「来年は母と旅行をしたい」
[ 2016年12月17日 13:45 ] 芸能
-

松本伊代、別荘に「絶対私のじゃない」ブラジャー ヒロミの浮気疑うも絶句…
[ 2016年12月17日 13:20 ] 芸能
-

ユーキャン 流行語大賞「日本死ね」に見解 議論認識も「意見言う立場にない」
[ 2016年12月17日 12:45 ] 芸能
-

青木崇高 優香と結婚生活は“次元”が違う「ニヤニヤしてしまいます」
[ 2016年12月17日 12:10 ] 芸能
-

内場勝則、島木譲二さん悼む「できませんを言わない一流ホテルみたいな人だった」
[ 2016年12月17日 12:02 ] 芸能
-

氷川きよし アニソン初挑戦!「DB超」OP曲 作詞は憧れ森雪之丞
[ 2016年12月17日 12:00 ] 芸能
-

山田洋次監督「母と暮せば」は選に漏れる 米アカデミー賞外国語部門
[ 2016年12月17日 11:57 ] 芸能
-

当て逃げ同乗のスーマラ武智が謝罪「どんな理由があったにせよダメなこと」
[ 2016年12月17日 11:30 ] 芸能
-

ロマンポルノ復活祭!
[ 2016年12月17日 11:00 ] 芸能
-

ほのかりん 所属事務所との契約解除 ゲス川谷と未成年飲酒
[ 2016年12月17日 10:57 ] 芸能
-

映画「湯を沸かすほど…」中野量太監督“熱い涙”止まらず 津川雅彦も「実に爽快」
[ 2016年12月17日 10:30 ] 芸能
-
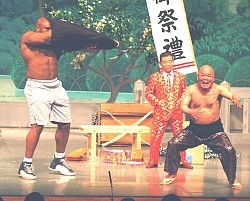
島木譲二さん訃報に後輩芸人から追悼の声続々 麒麟・川島「男のロマンだった」
[ 2016年12月17日 10:26 ] 芸能
-

中越典子が第1子妊娠を発表!「生命の神秘に感動」永井大、待望のパパに
[ 2016年12月17日 10:00 ] 芸能
-

厳しさは優しさ…脚本家・足立紳、長編映画監督に“罵詈雑言”妻認めた「面白い」
[ 2016年12月17日 09:30 ] 芸能
-

夢守るため…高畑淳子“思い出の家”売却へ 息子の示談金などに
[ 2016年12月17日 09:00 ] 芸能
-

清水富美加 庵野秀明氏が制作統括のアニメ「龍の歯医者」で声優初挑戦
[ 2016年12月17日 08:50 ] 芸能
-

島木譲二さん 元ボクサーでこわもても…いつもニコニコ気遣いの人
[ 2016年12月17日 08:35 ] 芸能
-

三谷幸喜氏「真田丸」振り返る 脚本に込めた思い「信繁は敗者の守り神」
[ 2016年12月17日 08:00 ] 芸能
-

三谷幸喜氏「真田丸」初回“浅間山”で爆笑手応え 次回大河はペンネーム?
[ 2016年12月17日 08:00 ] 芸能
-

「真田丸」三谷脚本はどう作られた?行間が深いワケ…“参謀”が明かす秘密
[ 2016年12月17日 08:00 ] 芸能
-

中島裕翔 トークも光った!?ツリー点灯式で「転倒しないよう…」
[ 2016年12月17日 06:45 ] 芸能
-

高畑充希、初の写真集発売 “すっぴん”でとと姉ちゃん卒業
[ 2016年12月17日 06:34 ] 芸能
-

解散「ViViD」ボーカルSHIN再出発 24日ソロ初ライブ
[ 2016年12月17日 06:20 ] 芸能
-

こじるり 高校ラグビーハイライト4年目「今や母性を感じる」
[ 2016年12月17日 06:09 ] 芸能
-

藤澤ノリマサと熱唱も華原朋美、プライベートで「夢やぶれて」は…
[ 2016年12月17日 06:00 ] 芸能
-

高橋メアリージュン 「新・ミナミの帝王」新作でメイド姿、ジュニア絶賛
[ 2016年12月17日 06:00 ] 芸能
-

大泉洋 歴史覆したい!?「幸村には死んでほしくないと」
[ 2016年12月17日 05:51 ] 芸能
-

テレ朝 成宮寛貴氏出演の「相棒」19日から再放送再開へ
[ 2016年12月17日 05:47 ] 芸能
-

ノンスタ石田、黒のスーツで相方の事故謝罪 解散は「しません」
[ 2016年12月17日 05:35 ] 芸能
-

吉本新喜劇で活躍「大阪名物パチパチパンチ」の島木譲二さん死去
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能
-

ピコ太郎「ドクターX」参上 手土産はヒョウ柄の風呂敷に…メロン
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能
-

「マッサン」エリー役 シャーロット・ケイト・フォックスが離婚
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能
-

キムタク 来年1月以降もラジオ番組名に「SMAP」残す
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能
-

「ゆずの葉ゆれて」の松原智恵子 ソチ国際映画祭で主演女優賞
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能
-

はやぶさクリスマス公演 700人前に新曲「流星のロマンス」熱唱
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能
-

冨田真由さんの手記公表 小金井刺傷被害、警察対応に不満
[ 2016年12月17日 05:30 ] 芸能

























