【球春ヒストリー(13)】1987年・PL学園 全員が一つになった3度目の優勝

Photo By スポニチ
謙虚に、ひた向きに――。そして全員が一つになって戦った。1987年の第59回大会でPL学園は3度目の優勝を飾ったが、下馬評は決して高くなかった。20打数7安打3打点の活躍を見せた片岡篤史氏(本紙評論家)が当時を回想する。
「とにかく一つ、校歌を歌いたかった。それだけだった。後に(当時のメンバーで)4人プロへ行ったというのはあるけれど、目標は全国制覇とかではなく一つ一つ勝っていくことだった。誰ひとり慢心はなかった。謙虚さ、ひたむきさがあったと思う」
清原和博、桑田真澄ら2学年上の世代は夏の甲子園大会を制するなど史上最強とも言われたが、1学年上は選抜で初戦敗退し夏は大阪大会準決勝で敗れ、甲子園出場を逃した。当時も前年秋の大阪大会3位で近畿大会ベスト4での選抜出場だったが、聖地で力を発揮できた強さの源には厳しい日常生活の中で育まれた連帯感があった。
「寮生活で生まれた、助け合う心で一つになれた。見栄えはよくなかったけど、高校生らしい戦いができた」
難敵相手に接戦の連続だった。1回戦で好左腕の石貫宏臣(元広島)がいた西日本短大付を破ると、準々決勝では芝草宇宙(元日本ハム)の帝京に延長11回サヨナラ勝ち。東海大甲府との準決勝は5回終了時点で1―5。それでも動じなかったのは「粘って粘って、粘り抜く」という強靱(きょうじん)な精神力と一つの経験則があったからだった。
86年11月8日に行われた近畿大会準々決勝・大商大堺戦。大阪大会準決勝で5安打零敗した相手に、またも苦戦を強いられ5回表を終えた時点で1―5と4点差を付けられた。負ければ選抜出場が絶望的となる一戦。選手を奮起させたのは中村順司監督(当時)の「今日は南の月命日だ。そんな顔してたら南が泣くぞ」の言葉だった。
同年6月8日に、同期で中軸として将来を嘱望されていた南雄介さんが急死。主将だった立浪和義はズボンのポケットに写真をしのばせ、片岡氏はベンチに遺影を立てかけていた。仲間のためにも――。思いが一つとなり8―5で逆転勝ちした。
同じような展開となった東海大甲府戦。6回に片岡氏の左翼線への2点二塁打など5安打集中して4点を奪い同点。2試合連続で延長に入ったが14回に3得点し決着をつけた。「一緒に戦い、背中を押してくれたと思う」。片岡氏の言葉に同期17人の思いが凝縮されていた。
甲子園大会で春夏合わせ7度の優勝を誇るなど一時代を築いた母校は、16年夏の大阪大会を最後に休部状態が続く。「これからOBで力を合わせたい」。OBだけではない。甲子園が、いや、全国の高校野球ファンが「永遠の学園」の復活を待っている。=おわり=
○…87年春の関東第一との決勝では相手のミスを逃さなかった。初回2死から立浪がストレートの四球で出塁。続く深瀬猛は飛球を打ち上げたが相手バッテリーが譲り合う形で取れずファウルとなり、直後の8球目を中堅左に運ぶ適時二塁打で先制点を奪うなど2点を先取した。7、8回に計5点を奪う7―1の完勝劇で、バックも無失策で投手陣を盛り立てた。片岡氏は「相手のミスにつけ込む。こちらはミスをしない。それがPLの野球」とうなずいた。
2020年4月1日のニュース
-
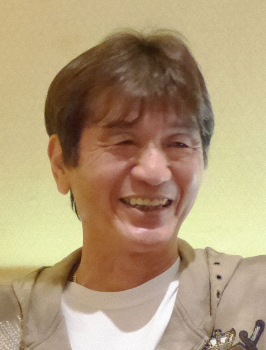
がん闘病中の大島康徳氏、ブログで悲痛な叫び「梨田!頑張れ!頑張れ!!頑張れ!!!」
[ 2020年4月1日 20:41 ] 野球
-

広島新庄・迫田監督退任 4度の甲子園導く、後任に宇多村コーチ
[ 2020年4月1日 20:08 ] 野球
-

東邦の森田監督が退任会見「十分な役割果たせた」、昨年のセンバツV
[ 2020年4月1日 18:30 ] 野球
-

ビーグルクルー、プロ野球選手登場曲のみ収録のベスト盤 6・10発売「My HERO」ほか
[ 2020年4月1日 18:00 ] 野球
-

中日 4班で接触避け“時差練習”、与田監督「大事なのは選手の健康」
[ 2020年4月1日 17:39 ] 野球
-

関大、同大など野球部活動休止 関西学生野球、6日に臨時常任委員会
[ 2020年4月1日 17:12 ] 野球
-

元楽天監督・梨田氏が新型コロナ感染 重度の肺炎で入院 近鉄、日本ハムでリーグ優勝
[ 2020年4月1日 16:22 ] 野球
-

堀内さん、政府に注文「早く具体的な支援策を出さないとみんな参っちゃうよ」
[ 2020年4月1日 15:37 ] 野球
-

東京六大学野球 5月中旬に開幕延期、5日に運営方法を協議
[ 2020年4月1日 15:32 ] 野球
-

パ・リーグ 手洗い啓発キャンペーン 4選手の手洗いシーン&好プレー動画公開
[ 2020年4月1日 14:12 ] 野球
-

阪神OBブラゼル氏がエール「ウイルスに打ち勝って」
[ 2020年4月1日 13:52 ] 野球
-

横浜高野球部 新体制発表 OBの村田浩明氏が監督就任「大役…一生懸命頑張っていきたい」
[ 2020年4月1日 11:55 ] 野球
-

夏の甲子園開催は大丈夫? クリアすべき3つの課題
[ 2020年4月1日 09:30 ] 野球
-

飲食店経営の元虎戦士も悲鳴…浅井良さん、葛城育郎さん、桟原将司さんが休業など苦渋の決断
[ 2020年4月1日 09:00 ] 野球
-

先行きの見えない日々…DeNA今永が見せてくれた「クスっとする」心遣い
[ 2020年4月1日 08:45 ] 野球
-
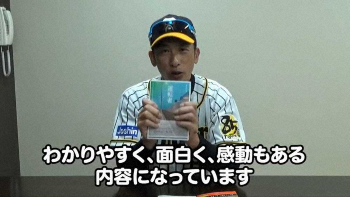
【内田雅也の追球】「経験」として受けいれる――阪神・矢野監督の愛読書から「運」を考える
[ 2020年4月1日 08:00 ] 野球
-

【オリックス】救世主になるか 好機に強い“掃除屋”ジョーンズ
[ 2020年4月1日 07:10 ] 野球
-

【ヤクルト】投手出身の監督はテコ入れ成功例が多い 高津監督にも兆し!!OP戦セ2位の防御率
[ 2020年4月1日 07:08 ] 野球
-

【球春ヒストリー(13)】1987年・PL学園 全員が一つになった3度目の優勝
[ 2020年4月1日 06:30 ] 野球
-

パ6球団 4・24開幕にNO!オンライン社長会議で一致 日程逆算よりコロナ終息待つべき
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

楽天・三木監督「今は我慢のとき」動画でファンにメッセージ
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

阪神 藤浪、伊藤隼、長坂が近日中にもPCR検査へ 退院条件に必要
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

巨人“無期限”解散延長 4・4までの予定が一変…原監督「非常に厳しい現実」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

ギリギリまで悩んだ末…ソフトB 無期限活動休止決断の背景
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

ヤクルト厳戒自主練習 投手、野手に分け時間も場所も分散
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

オリ全体練習中止 西村監督「大事なのはコロナに感染しないこと」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

DeNA伊藤光、TV電話で取材対応 開幕不透明も前向き「今だからできるトレーニングがある」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

中日 4・1から全体練習取りやめ 当面自主練習に
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

発熱の中日・平田、全体練復帰「花粉症で微熱出た」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

ロッテ・フローレス支配下登録 BC富山に感謝「最初に日本でプレーする機会をくれた」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

朗希、調整プラン白紙 ノースロー状態が10日近くに
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

ロッテ・井口監督、ファンから質問募集 1日10問ずつ 電話で回答
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

巨人・ディプラン 支配下登録「菅野投手のようになりたい」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

巨人・菅野 東京五輪延期「残念」も「今は自分ができることをしっかり」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

東京五輪延期、侍J選考に影響 朗希、奥川、清宮ら若手にチャンス
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

広島・誠也 東京五輪延期も「出たい」決意不変 開幕時期も「深く考えないように」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

日本ハム・矢野コーチが「オンライン打撃指導」開始 「動画で選手とコミュニケーションを取れるように」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

西武 山川&森、21年東京五輪「出たい」延期も侍入り熱望
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

西武・松坂「秘密兵器」木製バット提供 外崎も驚き「打球にいい回転のスピンがかかる」
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

NPB 稲葉監督の続投正式要請へ
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

阪神・新井貴浩は18年ぶり甲子園開幕を生涯忘れない――3・11 セパ同時開催へ戦い続けた選手会長
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

社会人野球、各地区大会の中止を検討 日本選手権も見通し立たず
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

大学野球、ほぼ全リーグが延期 大学選手権出場校決定のため順位決定方法を変更するリーグも
[ 2020年4月1日 05:30 ] 野球
-

マエケン SNSで日本のファンに呼びかけ「無駄な外出は減らして」
[ 2020年4月1日 02:30 ] 野球
























