内田雅也が行く 猛虎の地(20)甲子園球場 夢を見る、幸せが待つ野球場

Photo By 提供写真
【(20)甲子園球場】
春真っ盛りの日曜日で快晴、甲子園球場には人波が押し寄せた。1949(昭和24)年4月24日、阪神―巨人シーズン初対戦のダブルヘッダーはプロ野球始まって以来の大観衆となった。
スタンドは超満員。球場はラッキーゾーンにも観客を入れたが、それでも観客は詰めかけた。
第1試合の5回裏、ついにグラウンドの一、三塁側ベンチ横まで観客があふれた。公式記録に午後2時20分から28分間、試合中断とある。兵庫県警鳴尾署員約30人がロープを張るなど整理にあたり、進駐軍兵士が空砲を撃って騒乱を鎮めた。球場によると「観衆9万人を超えた」としている。
翌日のスポニチ本紙は1面で「甲子園未曽有の大観衆 グラウンドに波状攻撃」と見出しをとり、阪神ベンチ横まで観衆があふれた写真を大きく掲載している。
データベースの写真を拡大して見れば、ベンチ横の人びとの多くが笑顔でいる。特に丸刈り頭や学帽をかぶった少年たちが目立つ。その目は輝いているではないか。
<野球狂時代と言えば確かに、野球黄金時代が到来した感がある>と阪神監督兼投手・若林忠志が同年12月25日発行、自身監修の雑誌『ボールフレンド』に書いた。プロ野球創設36年から在籍する者として<終戦前、否、プロ野球の草分け時代を想起すると感無量なものがある>。
「ショーバイニンの野球」「職業野球」と卑下されたプロ野球が脚光を浴びていた。物も食糧もない時代、人びとはプロ野球に夢を託していた。
若林は終戦翌年の46年に「戦後、子どもたちの目の輝きが違ってきていた。この子どもたちは宝だ」と語っている。
終戦時、青森で9歳だった劇作家・寺山修司は<一日として野球をしなかった日はなかった>と書いている。<まだ街のあちこちに空襲の焦土が残っている広場に、私たちはゴムのボールを一つ、ポケットにしのばせて集まってきた>。66年、月刊誌『文藝春秋』に寄せたエッセー、その名も『野球の時代は終(おわ)った』である。
寺山はキャッチボールなど「する野球」が終わりを告げ、テレビなどで「見る野球」ばかりになったと指摘していた。
「野球の危機」が叫ばれて久しい。寺山の嘆きから半世紀以上、近年、小中学生をはじめ野球人口の減少が著しい。一方で、今年、プロ野球の観客動員は2653万6962人(1試合平均3万929人)で実数発表となった2005年以降でセ・パ両リーグとも最高を記録している。寺山の指摘は予言のようだ。
ただし「新時代」という見方もできる。するのも見るのも野球一辺倒ではなくなり、趣味や娯楽が多様化するのは、むしろ健全な成り行きではないか。問題は、人びとは野球に何を求めているのか、野球は何を提供できるのかである。
目指すのは、戦後から昭和にかけて見られた野球場である。
後楽園球場についてNHKアナウンサー・志村正順は<野球ファンの球場へ急ぐ気持ち、時間は十分あるけれど、まわりの急ぎ足につられて、思わず自分の足も早くなる。(中略)しまいには走りだす>とラジオ実況した。雑誌『野球少年』(芳文社)47年12月号「誌上録音放送」にある。
新資料、新証言が盛り込まれた元巨人球団代表・山室寛之の『プロ野球復興史』(中公新書)のオビには<野球界も日本も、もっとも元気だった頃><昭和とは、日本人すべてが白球に夢を託す時代だった>とある。
昭和について作家・重松清は自伝的な『娘に語るお父さんの歴史』(ちくまプリマー新書)で、父親に語らせている。「いまがたとえ不幸でも、未来には幸せが待ってると思えるなら、その時代は幸せなんだよ」
生きづらい世の中である。夢や希望を売るプロ野球に期待したい。
球団創立85周年を迎える阪神は歴史に学びたい。戦後、若林は自費で「タイガース子供の会」を立ち上げ、機関紙「少年タイガース」を発行し、野球教室を開催した。全国各地の施設を慰問して回った。活動を再評価した球団は2011年『若林忠志賞』を設け、社会貢献活動を奨励する。ファンサービス、地域密着、慈善活動……で人びとに寄り添いたい。
オーナーも球団社長も監督も選手も……もちろん勝利、優勝を目指すのだが、そんな目標の前に目的がある。甲子園球場に向かう人びとが思わず早足になり、試合を見れば明日への希望が湧く。タイガースはそんな野球を目指したい。
迎える2020年がどうか良い年でありますように。甲子園球場に願いを込めた。=敬称略=(編集委員)=終わり=
2019年12月28日のニュース
-

レッズ最有力も…秋山にBジェイズも興味 米専門局記者が言及
[ 2019年12月28日 21:21 ] 野球
-

ロッテ・アジャ井上、“本家”アジャ・コングから公認もらった!TV番組で熱い抱擁
[ 2019年12月28日 21:07 ] 野球
-

秋山翔吾 「ショボい」とダメ出しされた侍Jへの差し入れとは…ガックリ「買わなくてよかった」
[ 2019年12月28日 20:18 ] 野球
-

ヤクルトJr2年連続決勝T進出 本島先頭弾、佐藤南3ランで勝利貢献
[ 2019年12月28日 16:48 ] 野球
-

履正社・関本主将「負けない集団に」 夏春連覇へ覚悟
[ 2019年12月28日 16:35 ] 野球
-

オリックスJr福田拓翔、2回完全救援で勝利貢献 自己最速に迫る121キロマーク
[ 2019年12月28日 16:33 ] 野球
-

バファローズ☆ポンタも祝福 ファン歓喜「ポンタ婚だね」「ポンタは若月の義理の兄に…」
[ 2019年12月28日 14:48 ] 野球
-

DeNAJrが決勝T進出 小口陽喜が逆転サヨナラ弾
[ 2019年12月28日 12:31 ] 野球
-

山口俊 ブルージェイズと正式契約 球団社長「彼は活躍の幅が広い」
[ 2019年12月28日 09:32 ] 野球
-

現役生活に幕「早大三羽ガラス」大石 胸に抱く斎藤、福井へ感謝
[ 2019年12月28日 09:30 ] 野球
-

阪神・藤原オーナー、今年の漢字は拓「選手一人一人が新しい境地を拓いて」
[ 2019年12月28日 08:46 ] 野球
-

広島・菊池 残留表明 米挑戦封印「温かい球団に感謝しかないです」
[ 2019年12月28日 08:23 ] 野球
-

菊池、米挑戦を阻んだ“潮流” MLB二塁手は守備範囲より打力の時代に
[ 2019年12月28日 08:18 ] 野球
-

内田雅也が行く 猛虎の地(20)甲子園球場 夢を見る、幸せが待つ野球場
[ 2019年12月28日 08:00 ] 野球
-

オリックス若月、結婚!8歳年上の美人声優・立花理香さんに「ポンタ」人形に指輪付けプロポーズ
[ 2019年12月28日 05:33 ] 野球
-

広島・菊池 3億円残留!球団野手最高額 メジャー封印“広島愛”でポスティング期限前に決断
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

20年以上…村上 地元知事に直訴“熊本でヤクルト戦を”
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

日本ハム・輝星 アニマルなりきりトレで新人王目指す!直球の威力復活へ“原点回帰”
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

日本ハム・輝星 バスケトレも導入「肘や手首も強化したい」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

日本ハム・栗山監督 夢の新球場へ「来年は必ず勝ちます」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

巨人、原体制で5年ぶりリーグV 山口オーナー五輪イヤーを「巨人軍として盛り上げる」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

巨人・高橋 新妻がコーチ「二人三脚トレ」 約10種の体幹メニュー考案
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

楽天・大地 グループ納会にサプライズ登場「三木監督を胴上げするために頑張ります」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-
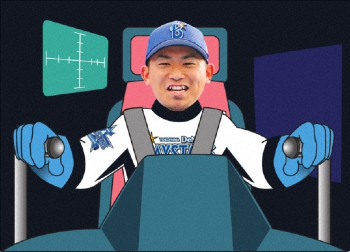
DeNA・今永 ガンダムトレで“アムロ化”だ!2年連続開幕&東京五輪へ「操縦士強化」意識
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

ソフトB・高橋純“マッチョ化”球速UPで来季初開幕1軍つかむ!先発も意欲「チャンスがあれば」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

阪神新助っ人ボーア あるぞ夫婦お立ち台!夫人はリポーター そろって日本語勉強中
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

阪神・近本、ノーモアブランク!“世界の盗塁王”福本氏から極意伝授
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

阪神 甲子園メインビジョンをマイナーチェンジ 映像改良でファンサービスの充実を
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

西武・栗山 松坂先輩とのお立ち台熱望「そうなったら最高」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

ロッテ「謎の魚」のど飴1年分で単年契約 紅白出場狙い「来年から生声を披露します。グフフフ」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

栗山 西武鉄道とのコラボツアー参加 52席限定ファンと“おいしい2時間”
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

7年連続Bクラス…中日・矢野社長 1点差負け×27試合に「3分の1をものにしていれば」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

オリ湊球団社長、最下位から巻き返しへ「芽は出ている。来年が楽しみ」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

楽天Jr劇勝発進!“スーパー小学生”大友が120キロ台連発
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

東大・青山 MBA取得へ米留学 家族に「何かの形で恩返しできれば」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

慶大 小原はアナウンサー挑戦!高橋亮はパイロット志望でANA内定
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

立大練習打ち上げ!中川 来年は先発転向「緩急をつけたい」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

マー君 ヤンキースと初コラボグッズ キャップ限定販売「かぶって球場に来てください」
[ 2019年12月28日 05:30 ] 野球
-

秋山と「レッズが交渉」大リーグ公式サイトも伝える
[ 2019年12月28日 02:30 ] 野球
-

ブルージェイズ合意 山口がメディカルチェック終え帰国
[ 2019年12月28日 02:30 ] 野球




























