ランはラン――阪神優勝へのサクランボ

Photo By スポニチ
【内田雅也の広角追球】大リーグ・カブスのカイル・シュワーバーは昨季、30本塁打を放った強打者だ。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦(シカゴ)では1回、ドジャース先発のダルビッシュ有のカットボールを左中間に先制のソロ本塁打を打ち込んだ。
だが、得点はこの1点のみ。1―6で敗れた。試合後、「ランはランだ」と印象的な言葉を残している。
英語で得点はラン。走ること、走塁のランをかけているのだ。
この談話を知ったのはフォローするニューヨーク・タイムズの野球記者タイラー・ケプナーのツイートだった。「いいね?」を押しておいた。
2番打者とはいえ、体重108キロの巨漢、盗塁も昨季は1個しかなかった。だからこそ、意味はより深くなる。
長距離打者であろうが、体形が太り気味であろうが、足が遅かろうが……野球は走ってこそ得点につながる、という根本的な姿勢を突いている。
阪神新外国人の4番ウィリン・ロサリオも100キロ級の巨漢で、長距離打者である。足も特別速いわけではない。それでも走る。次塁を狙う走塁に貪欲である。
キャンプ、オープン戦でその姿勢を存分に示している。3月3日、ヤフオクドームでのソフトバンク戦。4回表2死、振り逃げ(捕逸)で懸命に一塁に駆け抜け、出塁した。次打者・糸原健斗の一、二塁間突破の右前打で果敢に三塁を狙い、わずかに憤死となった。右翼手・城所龍磨の送球はハーフバウンドで、三塁手・松田宣浩の好捕・好タッチにあった。ギリギリのプレーだった。
回の合間、三塁コーチボックスに立つ作戦兼総合コーチ・高代延博が通訳を介してロサリオに語りかけていた。
「いや、責めはしなかったよ」と試合後、高代は言った。「回の最初と最後のアウトを三塁上で取られてはならない」という定説はあるが、前向き走塁の姿勢の方が重要である。「一塁でもう少しリードを取っていれば(三塁は)セーフだったな、と話したよ」
凡打疾走もすがすがしい。この日は1回表、当たり損ない、ボテボテ投ゴロに懸命に駆けた。
キャンプ中、2月27日の紅白戦(宜野座)では平凡な浅い中飛で二塁手前まで走っていた。高代は「ああ、あったね。ああした姿勢が若い選手たちの手本になる」とたたえていた。
3月の福岡で新外国人の激走を見て、1994年の平和台でのできごとを思い出した。ダイエー(現ソフトバンク)新外国人だったブライアン・トラックスラーである。
遊撃後方へ高い凡飛を打ち上げると、後に「コロコロちゃん」と呼ばれる丸い体形で懸命に駆けた。捕球された時には二塁まできていた。
その時、ダイエー担当記者の間から「全く打たんのに、走るのだけ必死で」と言い合う声が聞こえた。小バカにしたように笑っている。怒りがわいてきた。しばらく辛抱していたが、あまりに腹立たしく、記者席で立ち上がって言った。
「打ったら全力で走るのは当たり前じゃないですか!それを笑う記者の方が恥ずかしい」
まだ若く、年上の記者ばかりだった。笑い声は消え、シーンと静まりかえった。20年以上前の話だが、全力疾走を冷笑するような風潮は確かにあった。情けなかった。
恥の文化かどうか。日本の野球界には凡打疾走を恥じる心が昔からあったようだ。まだプロ野球誕生前、1931(昭和6)年、大リーグ選抜軍が初めて来日した。日本は東京六大学を中心に全日本軍を編成して戦ったが、全く歯が立たなかった。17戦全敗。大差の惨敗が相次いだ。
このとき全米軍の一塁手だったルー・ゲーリッグ(ヤンキース)が嘆いている。『日米野球史――メジャーを追いかけた70年』(波多野勝著・PHP新書)にある。
「日本に大和魂があると聞き、楽しみにして来た。だが残念ながら大和魂はどこにもなかった。凡打だと笑いながら一塁に走ってくる選手がいた。わたしはぶん殴ってやりたかった。大和魂のために」
痛烈である。「笑い」は照れ笑いか。全力疾走をムダと決めつけ、恥ずかしがる。それこそ恥ずべき姿勢である。
同書には戦前戦後を通じて、凡打凡走する日本の選手たちを嘆く大リーガーの話が数多く盛り込まれている。
日本のプロ野球で、凡打疾走が根付いたのは、ごく最近のことだと言えるだろう。トラックスラーが笑われた翌95年、野茂英雄が海を渡り、大リーグが身近になっていった。懸命に駆ける大リーガーたちを見習っていったのかもしれない。
今では、選手も記者も誰も笑わないはずだ。現阪神監督の金本知憲は2012年、現役引退会見で誇るべき記録を「連続フルイニング出場」よりも「連続打席無併殺打」と語っていた。2000―01年の1002打席連続無併殺打で、凡ゴロで懸命に一塁まで駆け抜けた証だ。自身の打率は下がるが、チームのための疾走だったわけだ。
さて、冒頭のシュワーバーはFAとなっていたダルビッシュがカブス入りし、チームメートとなったことを歓迎している。シカゴ・トリビューンによると、「チェリー・オン・ザ・トップ」と語っている。直訳すれば「てっぺんのサクランボ」。ショートケーキに乗せるサクランボのように「完璧にする最後のもの」という意味だそうだ。ジグソーパズルの最後のピース、日本で言う画竜点睛といったところか。
13年ぶり優勝を狙う阪神のサクランボはロサリオの持つ一発強打以上に「ラン」だろう。走力や機動力はもちろん、疾走するひたむきな姿勢が要点となる。=敬称略=(編集委員)
◆内田 雅也(うちた・まさや) 平和台球場記者席で声をあげた1994年当時は31歳。遊軍記者として阪神を中心に取材していた。同年7月、ゴルフの全米女子オープンなどの取材で米国特派を命じられると、合間に大リーグ・オールスター戦(ピッツバーグ)を取材した。日本人大リーガーはなく、日本人記者は数人だけだった。
2018年3月6日のニュース
-

青木 地元で活躍「この時期に宮崎でプレーできることに縁を感じる」
[ 2018年3月6日 20:04 ] 野球
-

中日の中軸候補・福田 今季オープン戦1号「一発で捉えることができた」
[ 2018年3月6日 19:49 ] 野球
-

おかわり オープン戦1号!「打てて良かった」と納得の表情
[ 2018年3月6日 19:22 ] 野球
-

巨人の新外国人ヤングマン 4回2失点「まだまだ満足できない」
[ 2018年3月6日 19:17 ] 野球
-

ロッテの新4番候補・井上 右方向へ逆転2ラン!「最高ですね」
[ 2018年3月6日 19:12 ] 野球
-

ロッテのドラ1・安田やっと出た!オープン戦初安打がサヨナラヒット!
[ 2018年3月6日 17:19 ] 野球
-

イチロー、マリナーズ復帰決定 メディカルチェックをパス あす入団会見
[ 2018年3月6日 15:00 ] 野球
-

藤浪、開幕ローテへ前進 最速152キロ、制球乱れず56球
[ 2018年3月6日 14:27 ] 野球
-

藤浪“開幕”前哨戦でロペスに3ラン被弾も4回7奪三振
[ 2018年3月6日 14:13 ] 野球
-

ロッテ 河合オーナー代行がチームを激励 全面サポートを約束
[ 2018年3月6日 12:12 ] 野球
-

地下鉄ラッピング車両 2018シーズン「ファイターズ号」7日から運行開始
[ 2018年3月6日 11:00 ] 野球
-

【キヨシスタイル】侍ジャパン 東京五輪へ出てこいキムタクばりスーパーサブ
[ 2018年3月6日 11:00 ] 野球
-

イチローとマリナーズの交渉は大詰め 1年契約で合意か
[ 2018年3月6日 10:51 ] 野球
-

ランはラン――阪神優勝へのサクランボ
[ 2018年3月6日 10:30 ] 野球
-

ダル、オープン戦初登板へ調整
[ 2018年3月6日 10:19 ] 野球
-

ロッテ「代打部屋」新設 狭かったZOZOマリンベンチ裏“リフォーム”
[ 2018年3月6日 10:16 ] 野球
-

前巨人・村田 BC栃木入団発表「自分の野球は変わらない」
[ 2018年3月6日 10:00 ] 野球
-

G阿部&坂本 BC栃木入団の村田にエール“また一緒に戦おう”
[ 2018年3月6日 10:00 ] 野球
-

田沢、8日に初登板「やるべき事をしっかりやるだけ」
[ 2018年3月6日 09:57 ] 野球
-

ロッテ 人工芝をリニューアル 選手、観客の目にも優しい設計
[ 2018年3月6日 09:46 ] 野球
-

DeNA・京山 鳥谷斬りでアピールへ「抑えれば良い経験になる」
[ 2018年3月6日 09:39 ] 野球
-

清宮、重さ変えて“相棒”探し「いろいろ使ってみる」
[ 2018年3月6日 09:35 ] 野球
-

“清宮効果”でチケット販売好調 開幕戦は完売見込み
[ 2018年3月6日 09:35 ] 野球
-

GT開幕戦に清宮差し込む!日テレがデビュー戦の2元中継検討
[ 2018年3月6日 09:35 ] 野球
-

広島・誠也10日にも今春初実戦守備 右足首骨折の昨年8月以来
[ 2018年3月6日 09:31 ] 野球
-

ヤクルト、ライアン&星復帰は5月?右肘手術後実戦メド立たず
[ 2018年3月6日 09:19 ] 野球
-

西武ドラ1斉藤大、開幕ローテ浮上 先発左腕不足で今月中旬にもテスト
[ 2018年3月6日 09:16 ] 野球
-

楽天・藤田1軍昇格へ 梨田監督が示唆「7日ぐらいから合流する予定」
[ 2018年3月6日 09:08 ] 野球
-

広島・丸、10日実戦守備復帰へ 右肩違和感で別メニュー挑戦中
[ 2018年3月6日 09:02 ] 野球
-

松坂“同期”上原と投げ合い心待ち 99年ともに新人王「同じ舞台でやりたい」
[ 2018年3月6日 09:00 ] 野球
-

DeNAドラ5桜井、甲子園凱旋 阪神2連戦で中継ぎ起用へ
[ 2018年3月6日 08:55 ] 野球
-

ロッテ、昨季は代打陣振るわず 1割台でリーグ5位低迷
[ 2018年3月6日 08:46 ] 野球
-

“ジョニデ似”左腕オルモス 2種のスプリット試す「風でどう変化するか」
[ 2018年3月6日 08:33 ] 野球
-

上原、巨人での役割は?沢村は評価急上昇、カミネロ&マシソンは当確
[ 2018年3月6日 08:22 ] 野球
-

大谷 マリナーズ復帰報道のイチローとの対決熱望「ぜひ一緒にできたら」
[ 2018年3月6日 07:46 ] 野球
-

イチロー古巣復帰 米名物記者「マ軍は一両日中に事態が固まることを希望」
[ 2018年3月6日 07:45 ] 野球
-

大谷 3打数無安打で途中交代、左中間に飛ばすも好守に阻まれる
[ 2018年3月6日 06:52 ] 野球
-

“巨人・上原”近日中に誕生 日本復帰へ決意の帰国「一日でも早く決めたい」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

巨人ドラ3大城、一塁挑戦!大型捕手に由伸監督“二刀流”即決
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

巨人・阿部 重信に逆方向の打撃伝授「投ゴロを打つ感覚で」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

巨人・陽岱鋼 右翼定位置獲りへ断酒「甘い考えはないように」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

阪神・藤浪“快幕”前哨戦へ意気込み「魅力あるボール投げたい」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

阪神ロサリオ、異例の猛練習 金本監督も“勤勉助っ人”評価
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

阪神・大山がチーム再合流 侍の経験糧に「学んだこと生かす」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

阪神チアの新ユニホームお披露目 白&ピンクにデザイン変更
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

オリ“山口高志2世”に熱視線 関大・山本ドラフト上位候補に
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

オリ金子、今季初登板へ調整 4・3本拠開幕戦へ照準
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

中日・柳 青木との“同郷対決”心待ち「しっかり自分の投球を」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

ソフトB内川 左ふくらはぎは軽度の筋膜炎「全然大丈夫」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

ヤクルト梅野OP戦初先発へ闘志 寺島好投が刺激「負けないように」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

セCSでも予告先発導入決定 西山理事長「機運が熟した」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

「野球くじ」導入の議論は行われず 12球団実行委員会
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-
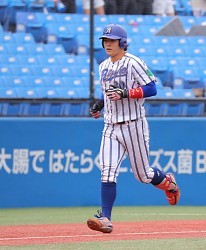
立正大・伊藤“東洋大三本柱”撃ちだ プロ注目右の大砲が闘志
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

上武大・吉田4失点反省 今秋ドラフト候補捕手「8連覇目指す」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

大谷、中6日で3度目登板へ 10日に4回70球を予定
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

平野“三度目の正直”で0封 三つ巴クローザー争いへ手応え
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

牧田、収穫の実戦2戦目“大胆シフト”経験「日本ではまずない」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

“屈強”マエケン インフル明けも好投「むしろ調子良かった」
[ 2018年3月6日 05:30 ] 野球
-

イチロー 古巣マリナーズとの契約合意間近、復帰なら6年ぶり
[ 2018年3月6日 03:14 ] 野球























