大リーグ公認歴史家に聞く米二刀流の系譜「大谷の登場に意味はある」

Photo By 提供写真
今オフにもポスティングシステムでメジャー移籍の可能性がある日本ハム・大谷翔平投手(23)の米国内での注目度ががぜん高まってきた。米球界で二刀流といえば、ベーブ・ルースが有名だが、草創期から20世紀初めにかけては他にも数多く存在した。ここに来て再び注目を集める二刀流選手の歴史を、大リーグ公認歴史家のジョン・ソーン氏(69)に聞いた。 (奥田秀樹通信員)
◎全盛期――19世紀、1チームはわずか10〜12人 病気やケガ以外の交代認められず
19世紀の大リーグは、投手も打撃の能力が高ければクリーンアップに座り、登板しない日は他のポジションを守った。大きな理由に、当時は1チームが10〜12人程度に決められていたという事情がある。そんな中でもソーン氏が「当時最高の二刀流」と挙げたのがガイ・へッカーの名だ。
ヘッカーは1882年〜91年に存在したプロリーグ、アメリカン・アソシエーションのコロネルズで主にプレーした。メジャー3年目の84年に52勝(20敗)、防御率1.85、385奪三振で投手3冠に輝き、外野手としても5試合出場。同年の打撃成績は投手としての出場時も含め、打率.297、4本塁打、42打点だった。
86年には28勝し、投手として大リーグ史上唯一の首位打者に輝いた。登板しない日は一塁、外野を務め、打率.341をマーク。ソーン氏は「8月15日は先発で勝利を挙げ打っては7打数6安打、3本塁打。投手の1試合3本塁打は初の快挙」と話す。
メジャー生活は9年。84年には73試合に先発し、670回2/3を投げるなどの酷使がたたった。肩肘のひどい痛みに悩まされ、90年限りで現役を引退。通算175勝を挙げ、野手としては一塁で322試合、外野で75試合に出場して通算812安打、19本塁打、打率.282だった。
◎衰退期――1900年以降にルール変更続出 選手枠拡大で野手増加
大リーグ草創期の二刀流全盛時代に一区切りをもたらしたのは、近代野球と呼ばれる1900年以降に相次いだルール変更だ。ソーン氏は「1891年に、それ以前は病気やケガ以外では許されなかった交代が認められるようになった。ベンチの選手数も少しずつ増えていった」という。1901年に1チームの選手枠が14人、08年17人、14年に25人となり、野手の控えが増えて分業化が進む。投手は打てなくても構わない――そんな流れが生まれ、投手の打撃レベルが一気に下がった。
しかし、二刀流は絶滅しなかった。20世紀の代表格はもちろんベーブ・ルースだが、ルースより13年遅い27年にメジャーデビューし、史上最強の打力を誇った投手ウェス・フェレルがいた。インディアンスなどで通算15年間で193勝を挙げ、20勝を6度マーク。通算38本塁打は、投手の最多記録だ。肩を痛めた33年のシーズン終盤は左翼手として13試合に出場している。
◎絶滅期――1960年代DH制の導入で分業化進行
大リーグは60年代に入ると、極端な「投高打低」の時代となった。そのため、ア・リーグが73年にDH制を採用。投手が打つ機会そのものが激減し、現在に至る。ソーン氏はこうした分業化の流れに異を唱え、大谷に期待を寄せる。
「私は大谷に二刀流でメジャーに来てほしい。分業が進んだため、プロとは思えない投手のお粗末な打撃やバントを見せられる。加えて25人の限られた選手枠でブルペン投手が増えたため、控え野手が少なく、監督は毎試合やりくりに頭を抱えている。大谷のような選手の登場はとても意味のあることだ」
カブスの知将ジョー・マドン監督はワールドシリーズを制した昨季、レギュラーシーズンでリリーフ左腕ウッドを3試合計5イニング、左翼で起用した。ジャイアンツのバムガーナーら、打撃に定評のある投手も少なくない。大谷が移籍すれば、しばらく米国で眠っていた偉大な二刀流の系譜をよみがえらせるかもしれない。
2017年9月5日のニュース
-
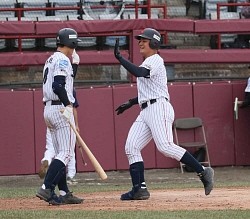
清宮に待望の一発!日本、南アフリカに7回コールド勝ち
[ 2017年9月6日 00:58 ] 野球
-

清宮、高校通算110号 16打数目で待望の大会1号
[ 2017年9月5日 23:59 ] 野球
-

巨人・寺内 4年ぶり本塁打がサヨナラ弾「プロ野球に入って一番」
[ 2017年9月5日 22:56 ] 野球
-
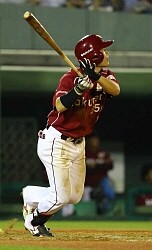
楽天 6点奪い新人の藤平を援護 梨田監督「久しぶりにつながった」
[ 2017年9月5日 22:52 ] 野球
-

ソフトB・サファテ 万感の日本新47S「最高のチームでプレーできるのが幸せ」
[ 2017年9月5日 22:50 ] 野球
-

巨人 逆転CSへ!9回宇佐見同点2ラン&11回寺内サヨナラ3ラン
[ 2017年9月5日 22:30 ] 野球
-

広島“安部劇場”でM再点灯 勝ち越し打2本の後でサヨナラ弾「最高でぇ〜す!」
[ 2017年9月5日 22:26 ] 野球
-

ソフトB 延長11回松田決勝打でM11 サファテ日本新47S
[ 2017年9月5日 22:24 ] 野球
-

日本ハム 今季の地方試合は2勝9敗…大谷の“不敗神話”も止まる
[ 2017年9月5日 22:20 ] 野球
-

広島の野間 自慢の快足で勝利を演出!「何でもいいからゴロで出ろ」に応えた
[ 2017年9月5日 22:18 ] 野球
-

ヤクルト石川 力投も援護なく10連敗…「結果がすべての世界」
[ 2017年9月5日 22:02 ] 野球
-

鳥谷、2000安打まであと4本 広島・野村から2安打
[ 2017年9月5日 21:48 ] 野球
-

広島 安部の劇的2ランでサヨナラ勝ち 4度目のマジック「12」点灯
[ 2017年9月5日 21:47 ] 野球
-

ロッテ CSの可能性消滅…伊東監督ため息「今日みたいなら来年も苦しそう」
[ 2017年9月5日 21:45 ] 野球
-

楽天ドラ1藤平 また連敗止めた ノーノーも「浮かんだ」7回1安打8K
[ 2017年9月5日 21:39 ] 野球
-

西武ドラ3源田、石毛に並んだ球団新人最多の127安打
[ 2017年9月5日 21:23 ] 野球
-

DeNA ウィーランド先制打&6回零封で連勝 筒香8回決勝弾 ヤクルトは8連敗
[ 2017年9月5日 21:22 ] 野球
-

楽天連敗10でストップ!ドラ1藤平また止めた!7回1安打零封2勝目
[ 2017年9月5日 21:15 ] 野球
-

広島・野村、今季10勝目お預け 5回4失点、勝利投手の権利得て降板も…
[ 2017年9月5日 20:22 ] 野球
-

阪神・藤浪、広島戦先発も4回5失点KO
[ 2017年9月5日 20:09 ] 野球
-

梨田監督去就 球団取締役会で議題になし 星野副会長「オーナーの専権事項」
[ 2017年9月5日 19:18 ] 野球
-

巨人・阿部が1打席のみで途中交代 代わって脇谷が4番・一塁
[ 2017年9月5日 18:50 ] 野球
-

ファーム情報 イースタン首位の巨人は打線爆発 24安打放ちロッテに大勝
[ 2017年9月5日 18:36 ] 野球
-

国学院のエース山岡 146球目でサヨナラ本塁打浴び「ツーシームが高めに…」
[ 2017年9月5日 18:24 ] 野球
-

東都大学で学生審判初採用!国士舘大3年の江尻さん ハーフスイングの判定も堂々
[ 2017年9月5日 17:48 ] 野球
-

6日の予告先発 巨人・田口―中日・大野ほか
[ 2017年9月5日 17:30 ] 野球
-

日本 開幕4連勝で女子野球のアジア杯優勝!
[ 2017年9月5日 17:16 ] 野球
-

日本ハム竹田球団社長 25年ぶり地元・富山での試合に「プロのプレーを肌で感じて」
[ 2017年9月5日 17:11 ] 野球
-

オリ 3人の助っ人の残留決定!ディクソン&マレーロとも契約延長
[ 2017年9月5日 16:43 ] 野球
-

15日の公示 楽天・藤平、阪神・西岡を登録
[ 2017年9月5日 15:52 ] 野球
-

巨人三軍 30日に釜石市で練習試合 東日本大震災の復興祈念
[ 2017年9月5日 15:15 ] 野球
-

東洋大・梅津 リーグ戦初登板で151キロ!ネット裏のスカウト「何年生だ?」
[ 2017年9月5日 15:02 ] 野球
-

イチロー 代打メジャー記録まであと4本 青木は3戦連続安打
[ 2017年9月5日 14:53 ] 野球
-

カブス2連敗 上原の登板なし 緊急降板のアリエッタ「問題ないと思う」
[ 2017年9月5日 14:09 ] 野球
-

マーリンズ 元中日チェンが4カ月ぶり復帰 メジャー初救援で1回零封
[ 2017年9月5日 13:32 ] 野球
-

Dバックス マルティネスが1試合4発 メジャー史上18人目
[ 2017年9月5日 12:55 ] 野球
-

ヤンキース 逆転で3連勝!レッドソックスは3連敗 ゲーム差2・5に
[ 2017年9月5日 12:39 ] 野球
-

イチロー 中前打で6戦ぶり快音 シーズン代打記録まであと4本
[ 2017年9月5日 11:27 ] 野球
-

思い出す99年の熱狂…福岡の夢を乗せた井口の打球
[ 2017年9月5日 10:40 ] 野球
-

【キヨシスタイル】清宮君、打力生かすためにも守備の意識を強く
[ 2017年9月5日 10:30 ] 野球
-

メジャー球団、8月以降大谷の視察急増 幹部クラスが来日
[ 2017年9月5日 09:06 ] 野球
-

Rソックス 大谷の二刀流OK「オープンな姿勢で見ている」
[ 2017年9月5日 09:04 ] 野球
-

ベーブ・ルース ヤ軍では打者専念も実は投手で5戦5勝
[ 2017年9月5日 09:02 ] 野球
-

大リーグ公認歴史家に聞く米二刀流の系譜「大谷の登場に意味はある」
[ 2017年9月5日 09:00 ] 野球
-

巨人、盤石の3本柱 史上初の防御率&勝利数3傑独占なるか
[ 2017年9月5日 08:10 ] 野球
-

猛虎に追い風!西岡が先発復帰へ「胸借りるつもりで攻めて行く」
[ 2017年9月5日 06:37 ] 野球
-

青木は5打数1安打1打点 メッツ移籍後3試合連続安打
[ 2017年9月5日 06:29 ] 野球
-

虎逆転Vへ“勝負の秋” 鳥谷「初戦が大事」糸井「全部出し切る」
[ 2017年9月5日 06:23 ] 野球
-

阪神・大山4番継続 98代目闘志メラメラ「頑張るだけ」
[ 2017年9月5日 05:55 ] 野球
-

金本監督、藤浪に先陣託した!大一番で“奇跡の扉”開けろ
[ 2017年9月5日 05:54 ] 野球
-

広島“新4番”松山が藤浪撃ち誓う「力負けしないように」
[ 2017年9月5日 05:53 ] 野球
-

おかわり2軍で3週間ぶり実戦「問題ない」8日に1軍昇格も
[ 2017年9月5日 05:50 ] 野球
-

ロッテ涌井、今オフ海外FA行使も 2度目取得「しっかり考えたい」
[ 2017年9月5日 05:47 ] 野球
-

ロッテ成田が1軍初合流 先発機会見据えて中継ぎ登板へ
[ 2017年9月5日 05:46 ] 野球
-

大谷、当面は野手で出場 次回登板は12日楽天戦以降か
[ 2017年9月5日 05:43 ] 野球
-

日本、スーパーラウンド進出!オランダに逆転勝ち 田浦4回9K
[ 2017年9月5日 05:41 ] 野球
-

中日・友利投手コーチが退任 編成部専念へ 森監督は続投示唆
[ 2017年9月5日 05:39 ] 野球
-

沢村、登板なく抹消 由伸監督「現時点で1軍では使えない」
[ 2017年9月5日 05:36 ] 野球
-

由伸監督、逆転CSへ“山の如し” 不振の陽&坂本へ変わらぬ信頼
[ 2017年9月5日 05:35 ] 野球
-

阪神、福留&西岡と来季も契約へ 両ベテランが虎の根幹支える
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

楽天・藤平、球団最悪タイ11連敗阻止だ!則本が頭下げ“懇願”
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

ソフト工藤監督“最速V”へ意欲 新調トロフィーに名刻む
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

巨人、山口俊の処分は「妥当」 選手会の「不当に重い」に反論
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

西武・雄星の反則投球問題 実行委は今後も議論継続
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

DeNA宮崎 打率首位奪回へ苦手ヤク攻略「役割果たせば数字も」
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

ヤク ギルメットが7日DeNA戦で来日初先発「凄く楽しみ」
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

清宮、燃えた2打点!絶不調もV犠飛 目の前で2度敬遠の屈辱
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-
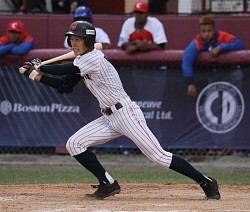
藤原&小園2年生コンビで7点 「熱盛!」でチーム鼓舞
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

左腕・山下が好投 低め徹底2失点「勝ててよかった」
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

古賀、初の先発マスクで攻守けん引 同部屋・中村と共闘誓う
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

キューバ指揮官 決定打不足嘆く「得点できなかった」
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

「プレミア12」19年11月開催 決勝は東京Dで
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

青木、古巣打ち3安打!2番に「喜び感じる」2打点&三盗
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

イチ歴代3位の代打91打席 前日の米新記録を訂正
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

ヤ軍&レ軍 ライバル同士でハリケーン被災支援基金を設立
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

ヤ軍・セベリーノ 球団53年ぶり23歳以下で200奪三振
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

8月度MVPにスタントン選出 アリエッタ、マチャドらも受賞
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

亜大“栄光の縦ジマ”復活 2シーズンぶりVへ伝統回帰
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

東洋大・飯田が連覇&日本一誓う「春の借りを返す」
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

小笠、佐々木ら6人がプロ志望届 10・26ドラフト会議
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

高野連、秋季地区大会の日程発表 北海道皮切りに全国で10大会
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

和歌山箕島球友会が劇的V4!タイブレークで逆転サヨナラ
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

大和高田ク無念の逆転サヨナラ負け 佐々木監督「この悔しさ糧に」
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球
-

埼玉アストライア逆転勝ちで2位浮上 谷山が2失点完投
[ 2017年9月5日 05:30 ] 野球























